エンゲージメントスコアとは?測定方法や向上による4つの効果を解説
組織状態の把握から分析・課題抽出までワンストップで実現
- エンゲージメントスコアとは
- エンゲージメントとは
- エンゲージメントスコアと従業員満足度の違い
- エンゲージメントスコアが注目されている3つの理由
- 人的資本経営を推進するため
- 労働人口の減少により人材を確保に力を入れる必要があるため
- 離職に関する課題を明確にするため
- エンゲージメントスコア向上による4つの効果
- 生産性・業績の向上に貢献する
- 離職率の低下につながる
- 従業員の自己肯定感・モチベーションが高まる
- 優秀な人材を惹きつけられる
- エンゲージメントスコアを高めるための5つのポイント
- エンゲージメントスコアの意味と指標を正しく把握する
- 評価制度の見直しと改善を行う
- 経営理念を社員に定着させる仕組みを構築する
- 社内のコミュニケーションを活性化させる
- エンゲージメントスコアを定期的に測定・可視化する
- エンゲージメントスコアの2つの測定方法
- パルスサーベイ
- センサスサーベイ
- おすすめのエンゲージメントスコア向上ツール「HRBrain」
- エンゲージメントスコア向上の2つの成功事例
- 人事業務効率化とエンゲージメント向上を推進|C-United株式会社
- 「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みを推進|株式会社鴻池組
- エンゲージメントスコアを高めて組織の生産性向上を目指す
近年、従業員の自発的な貢献意欲や組織への愛着を可視化する指標として「エンゲージメントスコア」が注目されています。
人材確保の難しさが増す中、単なる満足度では測れない組織との関係性の質を定量化し、経営改善や人的資本開示のKPIとして活用する企業が急増しています。
スコアを高めることで、離職率の低下、生産性の向上、モチベーションの強化、優秀人材の獲得といった好循環が生まれます。
本記事では、エンゲージメントスコアの意味や従業員満足度との違い、測定方法や向上による4つの効果について詳しく解説します。
また、エンゲージメントについてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連コンテンツもぜひご覧ください。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントスコアとは
エンゲージメントスコアとは、従業員や顧客が企業にどれだけ愛着や信頼、貢献意欲を持っているかを数値で示した指標です。
主にアンケートなどを通じて測定され、組織の健康状態や関係性の強さを可視化するために活用されます。従業員向けでは「従業員エンゲージメント」、顧客向けでは「顧客エンゲージメント」の評価に用いられます。スコアの改善は、離職率の低下や売上の向上など、経営成果にも直結します。
エンゲージメントとは
エンゲージメントとは、従業員が企業や仕事に対して持つ愛着心や貢献意欲、信頼の度合いを表す概念です。単に「会社が好き」という感情にとどまらず、組織の目標達成に向けて自発的に力を尽くそうとする積極的な心理状態を指します。
学術的には「ワークエンゲージメント」として「活力」「熱意」「没頭」の3要素で構成されると定義されています。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントスコアと従業員満足度の違い
エンゲージメントスコアと従業員満足度(ES)は、しばしば混同されますが、本質的に異なる概念です。
最大の違いは方向性にあります。従業員満足度が「企業から従業員への一方向の関係性」を測るのに対し、エンゲージメントは「従業員から企業への能動的な貢献意欲」と「双方向の関係性」を重視します。
具体的には、従業員満足度は給与・福利厚生・職場環境といった待遇面への満足度を測定し、主に受け身の状態を表します。
一方、エンゲージメントスコアは「仕事への情熱」「組織への共感」「自発的な貢献意欲」といった能動的な要素を捉えます。
実際に、エンゲージメントスコアが高い企業では、顧客満足度や企業価値の向上といった好循環が生まれやすいことが、さまざまな研究で実証されています。
現代の人的資本経営において、従業員満足度は衛生要因として一定水準を満たす必要がありますが、組織の成長を牽引するのは動機付け要因であるエンゲージメントといえるでしょう。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントスコアが注目されている3つの理由
ここでは、現代の経営環境においてエンゲージメントスコアがなぜ注目を集めているのかについて紹介します。 エンゲージメントスコアが注目されている主な理由は、以下の3つです。
<エンゲージメントスコアが注目されている3つの理由>
人的資本経営を推進するため
労働人口の減少により人材を確保に力を入れる必要があるため
離職に関する課題を明確にするため
人的資本経営を推進するため
近年、NECや富士通、ソニー、パナソニック、日立製作所などの大手企業が有価証券報告書やサステナビリティレポートでエンゲージメントスコアを開示・公表する動きが加速しています。
これは人的資本経営という新しい経営アプローチが広まっているためです。人的資本経営とは、従業員を資本として捉え、その価値を最大化することで企業の持続的成長を実現する考え方です。
経済産業省が推進する「伊藤レポート2.0」でも、エンゲージメントスコアは人的資本の重要なKPIとして位置づけられています。
投資家もESG投資の「S(社会)」の要素として従業員エンゲージメントを重視する傾向が強まっており、企業価値評価の重要な要素となっています。日本企業のエンゲージメントスコアの平均は国際比較で低い水準にあるとされ、2023年のデータによれば改善の余地は大きいといえるでしょう。
労働人口の減少により人材を確保に力を入れる必要があるため
日本は深刻な少子高齢化により、労働人口が急速に減少しています。厚生労働省の推計によれば、2030年までに約890万人もの労働力が失われるとされており、優秀な人材の獲得競争は今後さらに激化することが予想されます。
この環境下で企業が持続的に成長するためには、新規採用だけでなく、既存社員の定着率向上と一人ひとりの労働生産性向上が不可欠です。
エンゲージメントスコアは、こうした人材確保・定着戦略の効果を測る重要な指標となります。
近年、採用市場では、働きがいや成長機会を重視する傾向が強まっており、エンゲージメントスコアが高い企業は採用ブランディングにおいても優位性を持ちます。
離職に関する課題を明確にするため
エンゲージメントスコアが持つ実践的な価値のひとつが、離職リスクの早期発見と効果的な対策立案への貢献です。
離職率自体は結果指標であり、問題が顕在化した後の結果になりがちですが、エンゲージメントスコアは離職につながる潜在的な課題を事前に把握できる先行指標として機能します。
HRBrainなどのツールを活用すれば、部門別・属性別(役職、年齢層、勤続年数など)にエンゲージメントスコアを分析し、組織のどこにボトルネックがあるのかを明確にできます。
たとえば、「キャリア成長機会の不足」「上司との信頼関係の希薄さ」「仕事の意義や目的の見失い」といった具体的な課題が浮かび上がれば、それに応じた1on1ミーティングの活性化やキャリア形成支援、社内コミュニケーションの改善など、ピンポイントの対策を講じることが可能になります。
パルスサーベイによる定期的な測定と改善サイクルの構築により、離職率の低下と人材の定着が期待できるでしょう。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントスコア向上による4つの効果
ここでは、エンゲージメントスコアを向上させることで組織にもたらされる具体的な効果について紹介します。 エンゲージメントスコア向上による効果には主に以下の内容があります。
<エンゲージメントスコア向上による4つの効果>
生産性・業績の向上に貢献する
離職率の低下につながる
従業員の自己肯定感・モチベーションが高まる
優秀な人材を惹きつけられる
生産性・業績の向上に貢献する
エンゲージメントスコアの向上は、企業の生産性と業績に直接的な好影響をもたらします。エンゲージメントが高い従業員は、自発的に業務改善に取り組み、創意工夫を凝らし、高いパフォーマンスを発揮する傾向があります。
Gallup社の調査によれば、エンゲージメントの高い組織は低い組織と比較して、21%高い生産性、22%高い収益性、10%高い顧客満足度を示しています。
(参考:Gallup|Employee Engagement Statistics 2025: What Leaders Need to Know)
エンゲージメントスコアの測定には、HRBrainなどのツールが活用でき、JD-Rモデルにもとづく分析を通じて、各部門や従業員層ごとにエンゲージメントに影響を与えている要因を特定することが可能です。
これにより、ピンポイントで効果的な改善施策を実施し、生産性向上を図ることができます。
【関連コンテンツ】
離職率の低下につながる
エンゲージメントスコアの向上は、従業員の離職率を大幅に低下させる効果があります。エンゲージメントが高い従業員は、組織や仕事に対して強い愛着と貢献意欲を持っているため、簡単には転職を考えません。
離職率の低下は、採用コストや教育コストの削減だけでなく、組織知の維持やチームの安定性にも貢献します。
エンゲージメントスコアの継続的な測定と分析により、離職リスクの高い部門や属性を早期に特定し、1on1ミーティングやキャリア開発支援などの対策を集中的に実施することで、効果的に人材流出を防止できるでしょう。
【関連コンテンツ】
従業員の自己肯定感・モチベーションが高まる
エンゲージメントスコアを向上させる取り組みは、従業員の自己肯定感や内発的モチベーションを高め、仕事への熱意や没頭といったポジティブな心理状態を促進します。
ワーク・エンゲージメント理論によれば、エンゲージメントの高い状態とは「活力」「熱意」「没頭」の3要素が充足された状態です。
この状態にある従業員は、仕事に対して深い意義と充実感を感じ、自己実現に向けて主体的に取り組むようになります。
企業がエンゲージメントスコアの向上を目指して実施する施策の多くは、「仕事の意義の明確化」「成長機会の提供」「承認・称賛の文化醸成」「自律性の尊重」「良好な人間関係の構築」など、従業員の内発的モチベーションを刺激するものです。
例えば、定期的なバリュー浸透ワークショップの実施やピアボーナス・サンクスカード制度の導入により、従業員が自分の仕事と企業理念とのつながりを実感し、互いの貢献を認め合う文化が育まれます。
これらの取り組みにより、従業員は単なる満足を超えたやりがいや働きがいを実感できるようになります。
【関連コンテンツ】
優秀な人材を惹きつけられる
エンゲージメントスコアが高い企業は、採用市場での評判が向上し、優秀な人材を効率的に惹きつけられるという大きな競争優位を獲得できます。
少子高齢化による労働人口減少が進む日本では、人材獲得競争が一層激化しています。現代の求職者、特に若年層は給与や福利厚生といった条件面だけでなく、「働きがい」「成長機会」「企業文化・価値観」などの要素を重視する傾向が強まっています。
Great Place to Work®が発表している「働きがいのある会社」ランキングでは、従業員エンゲージメントが重要な評価基準となっており、上位にランクインする企業は採用市場での注目度が高まります。このランキングで上位に入る企業は、一般的な企業と比較して応募者数が多く、採用コストが低いという調査結果もあります。
エンゲージメントスコアを採用ブランディングの要素として戦略的に活用し、従業員の声を採用サイトやSNSで積極的に発信することで、企業と求職者のマッチング精度を高められるでしょう。
エンゲージメントスコアを高めるための5つのポイント
ここでは、組織内でエンゲージメントスコアを効果的に高めるための具体的な方法を紹介します。 エンゲージメントスコアを高めるためのポイントは、以下の通りです。
<エンゲージメントスコアを高めるための5つのポイント>
エンゲージメントスコアの意味と指標を正しく把握する
評価制度の見直しと改善を行う
経営理念を社員に定着させる仕組みを構築する
社内のコミュニケーションを活性化させる
エンゲージメントスコアを定期的に測定・可視化する
エンゲージメントスコアの意味と指標を正しく把握する
エンゲージメントスコアを向上させる第一歩は、その本質的な意味と適切な指標を組織全体で正しく理解することです。エンゲージメントは従業員満足度とは異なり、「組織への愛着」「仕事への熱意」「自発的な貢献意欲」を表す概念です。
多くの企業ではこの違いを曖昧にしたまま施策を展開しているため、本質的な改善に繋がっていません。エンゲージメントスコアの指標には、UWESと呼ばれる「活力」「熱意」「没頭」の3要素で測定する方法や、JD-Rモデルという「仕事の要求度と資源のバランス」で分析する手法、eNPSという組織推奨度を数値化する方法などがあります。
自社の課題や組織文化に合った指標を選ぶことが重要で、離職防止が課題なら「愛着」に関連する項目を、生産性向上が目的なら「熱意」や「没頭」に関する指標を重視するといった戦略的な選択が必要です。
指標を正しく把握するために、まずは人事部門が専門知識を習得し、経営層や管理職への研修を通じて組織全体の共通理解を促進することが、エンゲージメントスコア向上の基盤となります。
評価制度の見直しと改善を行う
評価制度はエンゲージメントスコア向上に大きな影響を与える重要な要素です。公正で透明性が高く、成長を促進する評価制度は、従業員の納得感やモチベーションを高め、エンゲージメントスコアの向上に直結します。
評価制度の見直しでは、まず「成果だけでなくプロセスも評価する」という視点が重要です。見直しをする際は、評価基準やフィードバックの方法を明確にすることで透明性を高め、従業員の不信感を払拭することが必要になります。
さらに、評価者である管理職の育成も不可欠です。適切なフィードバックやコーチングのスキルを持つ上司は、部下のエンゲージメントに大きな影響を与えます。
評価制度を単なる報酬決定の手段ではなく、従業員の成長を支援するツールとして位置づけ直すことで、エンゲージメントスコアの向上と組織全体の成長を同時に実現できるでしょう。
【関連コンテンツ】
経営理念を社員に定着させる仕組みを構築する
企業の経営理念やバリュー(価値観)が社員に深く理解され、日々の業務に活かされることは、エンゲージメントスコア向上の強力な推進力となります。
経営理念は、「なぜこの仕事をするのか」「自分の仕事がどのような社会的価値を生み出しているのか」という仕事の意義を示すものであり、ワークエンゲージメントの「熱意」の要素に直結します。
しかし、企業によっては理念が形骸化し、社内の壁に掲げられているだけになっているケースが少なくありません。
理念浸透のためには、経営層からの定期的な発信、理念やバリューを体現する行動を評価する仕組み、社員が理念について対話する機会の創出などが効果的です。
特に重要なのは、理念と日常業務のつながりを具体的に示し、社員一人ひとりが自分ごととして捉えられるようにすることです。
理念浸透は一朝一夕に達成できるものではなく、継続的な取り組みを通じて組織文化として根付かせていくことが大切です。
【関連コンテンツ】
社内のコミュニケーションを活性化させる
組織内の風通しの良いコミュニケーションは、エンゲージメントスコア向上に不可欠な要素です。JD-Rモデルでは「上司の支援」「同僚の協力」「情報共有」などが重要な仕事の資源として位置づけられており、良好なコミュニケーションはエンゲージメントの土台となります。
特に、従業員が自由に意見を述べ、失敗を恐れずチャレンジできる心理的安全性の高い環境を作ることが重要です。また、1on1ミーティングの定期開催は、上司と部下の信頼関係構築に効果的です。
リモートワークが普及した現在では、オンラインツールを活用した意図的なコミュニケーション機会の創出も欠かせません。
ビジネスチャットや社内SNSの導入、部門横断プロジェクトの促進、経営層と従業員の直接対話の場の設定など、多層的なコミュニケーションチャネルを構築することで、組織の一体感やエンゲージメントを高められます。
社内コミュニケーションの活性化は、単に頻度を増やすだけでなく、相互理解や信頼関係を深める質の高い対話を促進することが鍵となります。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントスコアを定期的に測定・可視化する
エンゲージメントスコアの向上を持続的に実現するためには、適切なツールと頻度で継続的に測定・可視化し、そのデータに基づいてPDCAサイクルを回していくことが不可欠です。
HRBrainなど可視化ツールを活用することで、組織の健康状態をリアルタイムで把握できます。測定方法としては、年に一度の詳細なセンサスサーベイと、より頻繁に実施する簡易的なパルスサーベイを組み合わせるハイブリッド型が効果的です。
センサスで特定した課題に対して改善施策を実施し、その効果をパルスサーベイで追跡することで、より機敏で実効性のある改善サイクルを回すことができます。
エンゲージメント測定で重要なのは「測って終わり」にならないことです。測定結果を迅速にフィードバックし、具体的な改善アクションに繋げる仕組みづくりが必要です。
たとえば、測定データを部門別・属性別に分析し、スコアが低い領域に対して集中的に施策を展開する、といった戦略的なアプローチが求められます。
エンゲージメントスコアの2つの測定方法
ここでは、エンゲージメントスコアを効果的に測定するための主要な手法について紹介します。 エンゲージメントスコアの測定方法は、以下の2つです。
<エンゲージメントスコアの2つの測定方法>
パルスサーベイ
センサスサーベイ
パルスサーベイ
パルスサーベイは、心拍(パルス)のように短期間で簡潔な質問を頻繁に繰り返し行う調査手法です。通常、設問数は10問以内と少なく、従業員が3〜4分程度で回答できる設計になっています。
週次や月次といった短いサイクルで実施されるため、組織の今の状態をリアルタイムに把握できる点が最大の特徴です。
HRBrainなどのツールでは、パルスサーベイ機能を通じて従業員の心理状態や職場環境に関する変化を素早く検知できます。
パルスサーベイのメリットは、以下の3つです。
回答時間が短く従業員の負担が少ないため、高い回答率が期待できる
時系列での変化や短期的な傾向を捉えやすい
集計も迅速なため、結果を現場の改善にすばやく反映できる
特に、新しい施策導入後の効果測定や、組織変革の進捗確認、離職リスクの早期発見などに適しています。
一方で、設問数が限られているため深い分析や包括的な課題把握には向かないというデメリットもあります。また、頻度が高すぎると「サーベイ疲れ」を引き起こす可能性もあるため、月1回程度の実施が現実的でしょう。
パルスサーベイは単独で使うよりも、後述するセンサスサーベイと組み合わせることで、その効果を最大化できます。
【関連コンテンツ】
センサスサーベイ
センサスサーベイは「全数調査」や「実態調査」を意味し、年に1回または数年に1回程度の頻度で、全従業員を対象に数十問以上の設問を用いて大規模に実施される調査です。
センサスサーベイの強みは、包括的で多面的な回答が得られるため、組織全体の風土や構造的な課題を深く掘り下げられる点にあります。
一方、設問数が多いため回答者への負担が大きく、参加率や回答の正確性が低下する可能性があることや、データの集計・分析に時間がかかり、改善策を現場に反映するまでにタイムラグが生じやすいことがデメリットとして挙げられます。
センサスサーベイの実施では、回答の匿名性確保や結果の透明な共有、具体的な改善計画の立案と実行が重要です。
おすすめのエンゲージメントスコア向上ツール「HRBrain」

エンゲージメントスコアの向上は、離職率の低下や生産性向上、優秀人材の確保など、組織に多くのメリットをもたらします。
中でも「HRBrain 組織診断サーベイ」は、エンゲージメントの可視化と改善サイクルを実現する優れたツールです。
センサス・パルスの両サーベイに対応し、部門・属性別に課題を特定。改善施策の実行と効果測定を一貫して行えます。人的資本経営を推進したい企業にとって、HRBrainは最適な選択肢です。
より詳しい情報や、貴社の課題に合わせた活用方法については、下記リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
エンゲージメントスコア向上の2つの成功事例
ここでは、実際の企業がエンゲージメントスコアを向上させた具体的な事例について紹介します。 エンゲージメントスコア向上の成功事例を自社での取り組みのヒントにしてみましょう。
<エンゲージメントスコア向上の2つの成功事例>
人事業務効率化とエンゲージメント向上を推進|C-United株式会社
「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みを推進|株式会社鴻池組
人事業務効率化とエンゲージメント向上を推進|C-United株式会社
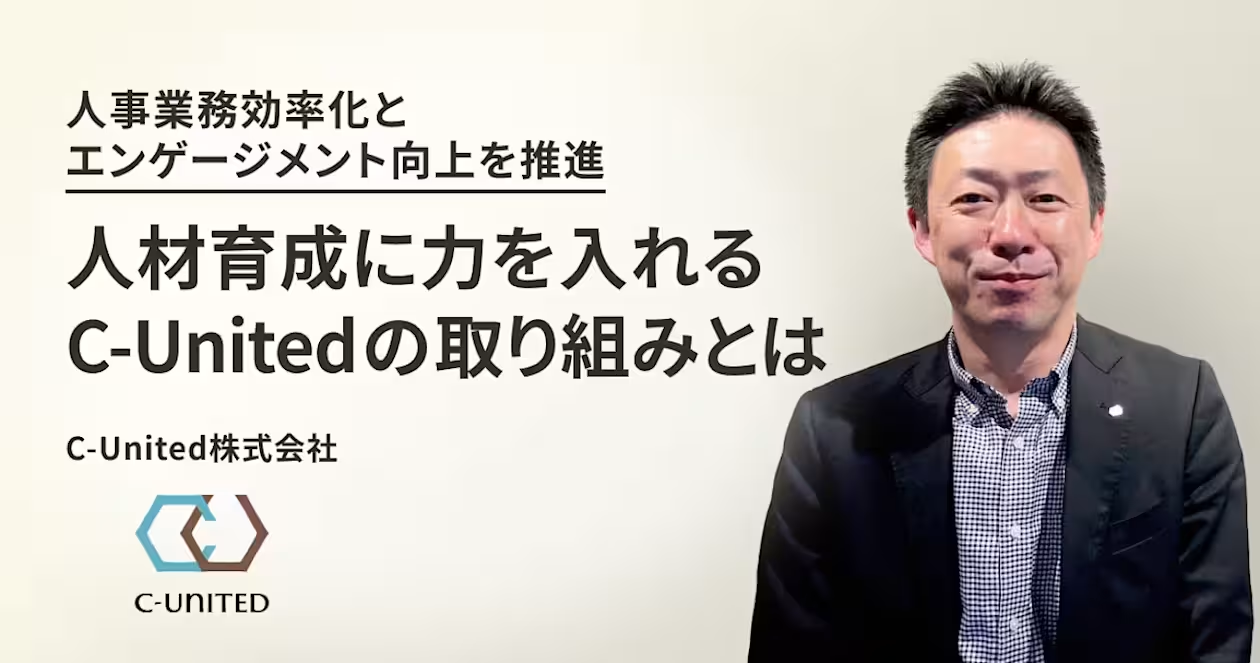
C-United株式会社では、人事業務の効率化と従業員エンゲージメントの向上を目的に、2021年11月よりHRBrainを導入しました。導入の背景には、紙ベースでの人事評価運用により年間1,700時間もの作業が発生していたことに加え、会社統合やコロナ禍による先行き不安が退職増加につながっていたという課題がありました。
対応策として、人事評価制度をHRBrainに移行し、評価項目の統一や導入後の運用サポートを受けながら評価プロセスの整備を進めました。
さらに、2022年8月には組織診断サーベイ「EX Intelligence」も導入。サーベイ結果を等級や役職などの属性別に分析することで、組織の課題を可視化し、特定セグメントにおけるスコア低下などの傾向を把握したうえで、的確な改善策を講じています。
その結果、評価業務の工数を大幅に削減できたことで、人材育成や評価の納得性向上といった本来注力すべき領域にリソースを振り向けることが可能になりました。
可視化されたサーベイデータは、エンゲージメント向上に向けた施策立案にも活用されています。今後は、評価結果とサーベイ結果を掛け合わせた統合的な分析を進め、タレントマネジメントの高度化を通じて、経営理念の実現を目指していく方針です。
【関連コンテンツ】
「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みを推進|株式会社鴻池組

株式会社鴻池組では、従業員エンゲージメントの向上と人的資本経営の実現に向け、2022年9月にHRBrainの組織診断サーベイ「EX Intelligence」を導入しました。
背景には、入社後のミスマッチによる早期離職や、理念の浸透不足といった課題があり、従来の満足度調査から脱却し、実感値と期待値のギャップに着目したエンゲージメント調査への切り替えが求められていました。
導入にあたっては、「従業員エンゲージメント業界No.1」を掲げた長期ビジョンに基づき、従業員と企業の双方向の関係性を重視した施策を推進。直感的な操作性やスピーディな結果確認が可能な点、HRBrainの丁寧なサポート体制も導入の決め手となりました。
EX Intelligenceの活用により、部署ごとのエンゲージメント傾向を可視化できるようになり、経営層や現場への具体的なフィードバックが可能となりました。
また、若手層への研修や部門別の対話機会創出など、サーベイ結果に基づいた施策実行にもつながっています。加えて、EXスコア®︎を中期経営計画のKPIとして活用することで、組織状態の定量的な把握と改善を継続的に進める土台が整いました。
今後も健康経営やダイバーシティ施策と連動しながら、社員一人ひとりに寄り添い、企業と人材がともに成長できる組織づくりを目指していく方針です。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントスコアを高めて組織の生産性向上を目指す
エンゲージメントスコアは、従業員の仕事への熱意や企業への愛着を数値化し、離職率の低下や業績向上につながる重要な経営指標です。
満足度では捉えきれない能動的な貢献意欲を把握することで、組織の成長に直結する打ち手を講じられます。人的資本経営の潮流の中で注目が高まる今こそ、まずは自社のスコアを正しく測定・分析し、現状を可視化しましょう。
そして、理念浸透や評価制度の改善、コミュニケーション活性化といった施策を通じて、エンゲージメントを高める取り組みを始めましょう。







