エンゲージメントサーベイは意味ない?効果が出ない原因と実施方法を解説
組織状態の把握から分析・課題抽出までワンストップで実現
- エンゲージメントサーベイは本当に意味ない?
- エンゲージメントサーベイとは?
- エンゲージメントサーベイが意味ないと思われてしまう5つの理由
- 目的や活用方法が社内で共有されていない
- 質問内容が抽象的すぎて、現場の課題や従業員の本音を拾えていない
- 情報の取り扱いへの配慮が不足し、従業員が正直に回答できない
- 調査結果を受けた改善策の提示やフィードバックが行われていない
- 一度きりで終わる取り組みになっており、継続的な改善につながっていない
- エンゲージメントサーベイが効果的に活用できる4種類の企業の特徴
- 離職率が高く、人材定着に課題を感じている企業
- 組織の一体感やチームワークが希薄だと感じている企業
- マネジメント層と現場の温度差がある企業
- 評価制度や働き方改革を進めたい企業
- 効果的なエンゲージメントサーベイの6ステップの進め方
- 1.目的とゴールを明確にする
- 2.設問設計と対象者の選定を行う
- 3.従業員へ事前説明を行い、心理的安全性を確保する
- 4.サーベイを実施し、集計・分析する
- 5.結果を共有し、フィードバックを行う
- 6.改善アクションを具体化・実行する
- エンゲージメントサーベイを無駄にしない5つの活用方法
- 調査結果を見える化し、課題を明確にする
- 部門ごとの傾向を分析し、ピンポイントで対策する
- 従業員とのフィードバックセッションを設ける
- 改善アクションに落とし込み、すぐ実行に移す
- アクションの効果を測定し、再サーベイに活かす
- エンゲージメントサーベイを効果的に実施した3つの事例
- 全社を巻き込むサーベイ運用。各部門が主体となって進める組織改善の仕組みとは
- 「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善
- おすすめのエンゲージメントサーベイ実施ツール「HRBrain」
- エンゲージメントサーベイを「意味ない」で終わらせず、組織改善に活かしましょう
エンゲージメント向上のために多くの企業が導入するエンゲージメントサーベイですが、実際に「効果を感じられない」「意味があるのかわからない」といった声も少なくありません。
これは、単にサーベイを実施するだけでなく、結果の活用方法や組織全体への落とし込み方に課題があることが原因です。
本記事では、エンゲージメントサーベイが「意味ない」といわれてしまう背景を整理したうえで、真に効果を引き出すための実施手順と活用のポイントを詳しく解説します。
エンゲージメントサーベイは本当に意味ない?
エンゲージメントサーベイは「意味がない」と感じられることがありますが、その多くは運用方法に原因があります。目的や活用方法が社内で共有されていなかったり、抽象的な質問設計により現場の課題を拾えなかったりすると、従業員は形だけの調査と感じてしまいます。
さらに、調査後に改善策が示されず、何も変わらなければ「やっても意味がない」と捉えられるのも無理はありません。
しかし、目的を明確にし、心理的安全性を確保したうえで実施・分析し、フィードバックと改善アクションまで丁寧に行えば、サーベイは強力な組織改善ツールになります。
エンゲージメントサーベイとは?
エンゲージメントサーベイとは、従業員一人ひとりが企業や自身の仕事に対して抱いている自発的な貢献意欲や深い愛着心、すなわち「エンゲージメント」を数値化し把握するための調査手法です。
この調査は、単に待遇や職場環境への満足度を測る従業員満足度調査とは本質的に異なります。満足度調査が主に労働条件への評価に焦点を当てるのに対し、エンゲージメントサーベイは、従業員の仕事への情熱、組織目標達成への主体的な関与といった、より積極的で内面的な結びつきの強さを明らかにします。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントサーベイが意味ないと思われてしまう5つの理由
ここでは、エンゲージメントサーベイが「意味ない」という残念な評価を受けてしまう主な理由を5つの観点から深掘りし、それぞれの対策のヒントを提示します。
エンゲージメントサーベイが形骸化し、その真価を発揮できない背景には、主に以下の要因が考えられます。
<エンゲージメントサーベイが意味ないと思われてしまう5つの理由>
サーベイの目的や結果の活用方法が社内で不明確であること
設問が曖昧で、現場の実態や従業員の真意を捉えきれていないこと
個人情報保護や匿名性への配慮が不十分で、率直な回答が得られないこと
調査後の具体的な改善行動や従業員へのフィードバックが欠如していること
サーベイが単発で終わり、継続的な組織改善のサイクルに組み込まれていないこと
目的や活用方法が社内で共有されていない
エンゲージメントサーベイの実施目的や、集めたデータをどのように活かすのかという具体的な計画が、社内で従業員一人ひとりにまで明確に伝わっていない場合、サーベイそのものが「意味のない活動だ」と見なされてしまう大きな原因となります。
従業員が調査の目的を理解できなければ、調査への協力的な姿勢は生まれにくく、どうしても形式的で表面的な回答が増えてしまいがちです。また、企業側にとっても、目的が曖昧なままでは、集まったサーベイ結果を分析する際の視点が定まらず、本当に取り組むべき課題の特定が難しくなります。
その結果、具体的な改善策も的外れなものになったり、実行に至らなかったりするため、サーベイの価値を誰も実感できないという悪循環に陥ってしまいます。
サーベイ開始前には、その目的、期待される効果、結果をどう活用していくのかという計画を、経営層から全従業員に至るまで、透明性を持って丁寧に説明し、納得と共感を得ることが成功の第一歩です。
質問内容が抽象的すぎて、現場の課題や従業員の本音を拾えていない
エンゲージメントサーベイで使用する質問の内容が、あまりにも曖昧であったり、従業員が実際に働いている現場の実態と大きくかけ離れていたりすると、従業員の本当の気持ちや、現場が抱える具体的な課題を的確に捉えることができません。
これでは、せっかく調査を実施しても、表面的な情報しか得られず、「意味のないサーベイだった」という結果に終わってしまいます。従業員が質問の意図を正確に理解できなかったり、自分の状況や考えを表現するのに適切な選択肢が見つからなかったりすれば、正直で具体的な回答をすることは難しくなります。
たとえば、「あなたは会社の方針に満足していますか?」といった漠然とした質問では、従業員が具体的に何に満足し、何に疑問を感じているのかという核心には迫れません。
より効果的なのは、「〇〇という新しい人事制度について、あなたの業務にどのような影響がありましたか。具体的なエピソードを交えて教えてください」のように、具体的かつ従業員の経験にもとづいた意見を引き出す質問です。
サーベイの質問項目は、その目的と照らし合わせ、現場の状況を考慮しながら慎重に設計することが、価値ある洞察を得るために不可欠です。
【関連コンテンツ】
情報の取り扱いへの配慮が不足し、従業員が正直に回答できない
エンゲージメントサーベイで収集される回答の匿名性がしっかりと守られるのか、また、個人情報がどのように取り扱われるのかといった点について、従業員が心から信頼できない場合、正直な意見は集まりにくく、サーベイは信頼性の低いものになってしまいます。
従業員が「この回答によって、後で自分が不利益を被るのではないか」といった不安やおそれを感じてしまうと、それが本音を語る上で最も大きな壁となるからです。
特に、会社の体制や直属の上司に対する率直な意見、組織が抱えるデリケートな問題点に関する指摘は、従業員が「これを言っても大丈夫だ」という心理的な安全性を感じられなければ、決して表明されることはありません。
調査結果を受けた改善策の提示やフィードバックが行われていない
エンゲージメントサーベイを実施し、従業員から貴重な意見を集めたにもかかわらず、その調査結果が社内で適切に共有されなかったり、具体的な改善行動に結びつかなかったりする場合、従業員は「結局、自分たちの声は届かないのだ」「サーベイに協力しても何も変わらない」という無力感を抱き、調査そのものへの信頼を大きく損ねてしまいます。
従業員は、自身の時間と労力をかけて真剣にサーベイに回答する際、そのフィードバックが組織に受け止められ、職場環境の改善や問題解決といった何らかの前向きな変化に繋がることを期待しています。この期待が裏切られ、具体的なアクションや組織からのフィードバックが全く伴わない状態が続くと、従業員のエンゲージメントは向上するどころか、かえって低下してしまう危険性すらあります。
「サーベイ疲れ」や「どうせ回答しても無駄」といった諦めの感情を組織内に蔓延させる原因のひとつといえるでしょう。
【関連コンテンツ】
一度きりで終わる取り組みになっており、継続的な改善につながっていない
エンゲージメントサーベイが一度きり実施され、その後のフォローアップや継続的な改善活動へとつながっていない場合、その効果は非常に限定的なものになるか、あるいはほとんど効果を実感できないまま、「やはり意味がなかった」と結論づけられてしまうことが少なくありません。
従業員のエンゲージメントの状態や組織が抱える課題は、市場環境の変化、社内体制の変更、新しいメンバーの加入や退職といったさまざまな要因によって、常に変化し続けるものです。そのため、ある一時期に実施したサーベイで得られた結果というのは、あくまでその時点での組織の一断面を捉えたスナップショットに過ぎません。
その結果だけを頼りに、持続的な組織改善を実現することは極めて困難です。例えば、数年前に一度だけ大規模なサーベイを行い、当時はいくつかの改善策を講じたものの、その後は特に同様の調査も改善活動の進捗確認も行わなかった企業では、一時的に改善した指標も時間と共に元に戻ってしまったり、新たな問題が発生してもそれに気づく機会を失ってしまったりする可能性があります。
エンゲージメントサーベイを真に組織の力とするためには、定期的な実施を計画に組み込み、その結果を基にした改善活動を、組織運営の継続的なサイクルとして定着させることが重要です。
エンゲージメントサーベイが効果的に活用できる4種類の企業の特徴
ここでは、エンゲージメントサーベイを特に効果的に活用し、組織改善につなげやすい企業の特徴を4つのタイプに分類して解説します。自社がこれらの特徴に当てはまるか確認することで、サーベイ導入の優先度や目的設定のヒントが得られます。
エンゲージメントサーベイが組織の課題解決に貢献しやすい企業には、主に以下のような特徴が見られます。
<エンゲージメントサーベイが効果的に活用できる4種類の企業の特徴>
高い離職率に悩み、優秀な人材の定着が経営課題となっている企業
組織内の一体感やチーム間の連携が不足していると感じる企業
経営層や管理職と、現場従業員との間に認識や意識のギャップが存在する企業
人事評価制度の見直しや、より良い働き方の実現に向けた改革を目指している企業
離職率が高く、人材定着に課題を感じている企業
従業員の離職率の高さや、なかなか人材が定着しないといった課題は、多くの企業にとって深刻な経営問題です。このような状況にある企業にとって、エンゲージメントサーベイは問題の根本原因を突き止め、効果的な対策を講じるための強力な武器となり得ます。
なぜなら、従業員が退職を考える背景には、給与や福利厚生といった待遇面だけではなく、仕事そのものへのやりがい、キャリア成長への期待、職場の人間関係、組織全体の文化といった、エンゲージメントに深く関わる多様な要素が複雑に絡み合っているケースが多いからです。エンゲージメントサーベイを用いることで、これらの目に見えにくい要因に関する従業員の率直な意見や認識をデータとして可視化できます。
たとえば、「キャリアパスが不明確で将来に不安を感じる」「自分のスキルを活かせる機会が少ない」といった声が明らかになれば、それに対してピンポイントで育成制度の拡充や面談機会の増加といった的確な離職防止策や定着支援策を計画・実行することが可能になります。退職者の声だけでは拾いきれない、現在働いている従業員の本音に耳を傾けることが、人材流出を防ぐ第一歩です。
【関連コンテンツ】
組織の一体感やチームワークが希薄だと感じている企業
「最近、社員同士の連携がうまくいっていない気がする」「部署間の壁が高く、組織としての一体感があまり感じられない」といった悩みを持つ企業は少なくありません。
このような組織の一体感の欠如や、チームワークの機能不全を感じている企業にとって、エンゲージメントサーベイは有効な診断ツールとなります。従業員のエンゲージメントは、部門を超えた円滑なコミュニケーション、風通しの良い情報共有、互いを尊重し合える良好な人間関係といった、職場の環境や風土に大きく影響を受けるからです。
エンゲージメントサーベイを通じて、これらの要素に関する従業員の現在の認識や具体的な意見を客観的に把握することで、データにもとづいた組織風土の改革や、社内コミュニケーションを活性化させるための具体的な施策を効果的に立案し、実行に移すことが可能になります。
たとえば、サーベイ結果から「他部署の業務内容や目標への理解が不足している」「部門横断的な協力体制を築くための機会が少ない」といった課題が明らかになれば、部門交流を促進するワークショップの開催や、情報共有プラットフォームの導入といった具体的な対策を検討できます。
【関連コンテンツ】
マネジメント層と現場の温度差がある企業
経営層や管理職が「組織は上手く回っているはずだ」「社員は今の経営方針に満足しているだろう」と考えていても、実際に日々現場で業務に取り組んでいる従業員は全く異なる認識や不満を抱えている、というケースは珍しくありません。
このような経営・マネジメント層と現場従業員との間の認識のズレが生じている企業にとって、エンゲージメントサーベイはそのギャップを客観的なデータにもとづいて明確に可視化し、共通理解を形成するための効果的な手段となります。
なぜなら、経営層が良かれと思って推進している様々な方針や施策も、それが現場の従業員の実際のニーズや感情と乖離していては、従業員からの真の共感や自発的な協力を得ることは難しく、結果としてエンゲージメントの向上には結びつかないからです。
エンゲージメントサーベイは、経営判断や施策立案の前提となるべき現場の実態や従業員の意識を正確に把握し、より効果的な意思決定をサポートするための重要な情報を提供してくれます。
【関連コンテンツ】
評価制度や働き方改革を進めたい企業
従業員一人ひとりの貢献や努力を公正に評価する新しい人事制度の導入を検討していたり、多様化する従業員のニーズに応じた、より柔軟で生産性の高い働き方への改革を目指している企業にとって、エンゲージメントサーベイは重要な役割を果たします。
現状の制度や働き方に対する従業員の意識や満足度、課題感を正確に把握し、さらに導入した新しい施策が実際にどのような影響を与えているのかを測定・改善していくための羅針盤となるからです。
新しい人事評価制度や働き方に関するルールを導入・改定する際には、それらの変更が従業員にどのように受け止められ、日々の業務遂行、モチベーション、組織全体のエンゲージメントにどのような変化をもたらしているのかを、継続的に客観的に把握することが不可欠です。
エンゲージメントサーベイは、実施した施策の適切性を従業員の視点から検証し、より実効性が高く、従業員が真に納得し、働きがいを感じられる制度や環境へと改善・進化させていくための、客観的で貴重なデータを提供してくれます。
新しい評価制度導入後に「評価の公平性」に関するスコアを注視したり、リモートワーク推進後に「コミュニケーションの質」や「孤独感」に関する項目を測定したりすることで、具体的な改善点を発見で切るでしょう。
【関連コンテンツ】
効果的なエンゲージメントサーベイの6ステップの進め方
ここでは、エンゲージメントサーベイを形骸化させず、真に組織改善につなげるための具体的な進め方を6つのステップに分けて解説します。各ステップのポイントを押さえることで、サーベイの有効性を最大限に高めることができます。
主なステップは以下の通りです。
<効果的なエンゲージメントサーベイの6ステップの進め方>
- サーベイの目的と達成すべきゴールを明確に定義する
- 目的に合致した設問を設計し、調査対象者を選定する
- 従業員へサーベイの趣旨を丁寧に事前説明し、安心して回答できる心理的安全性を確保する
- 計画通りにサーベイを実施し、収集したデータを客観的に集計・分析する
- 分析結果を従業員と共有し、建設的なフィードバックの機会を設ける
- サーベイ結果から導き出された課題に対する具体的な改善アクションを計画し、実行に移す
1.目的とゴールを明確にする
エンゲージメントサーベイを効果的に進めるための最初のステップは、この調査を通じて「具体的に何を明らかにしたいのか」「最終的にどのような組織の状態を目指すのか」という目的とゴールを明確に定めることです。
サーベイの目的が曖昧なままでは、どのような質問項目を設定すべきか、集まった多くのデータをどのように分析し解釈すべきかといった、調査全体の方向性が定まりません。また、達成すべきゴールが不明確であれば、サーベイ結果を評価する際の基準や、具体的な改善アクションへと繋げるための判断軸を持つことができず、結果として「調査はしたけれど、結局何も変わらなかった」というやりっぱなしの状態に陥ってしまうリスクが非常に高くなります。
例えば、「最近、若手社員の離職が増えている。その根本原因を特定し、半年以内に定着率を昨年度と比較して5%改善するための具体的な施策を3つ立案し実行する」といった具体的な目的とゴールを設定します。
サーベイの質問項目もおのずと若手社員の仕事観やキャリア観、人間関係、労働環境など、離職に関連する可能性のある要因に絞り込まれ、その後の結果分析も目的達成に向けた要因特定と施策立案に集中できます。
2.設問設計と対象者の選定を行う
エンゲージメントサーベイの目的とゴールが明確に定まったら、次に行うべき重要なステップは、その目的に合致した質の高い設問を慎重に設計し、調査から適切な情報を得るための対象者を具体的に選定することです。
設問の質が低かったり、質問内容がサーベイの本来の目的とズレていたりすると、たとえ多くの従業員から回答を集めたとしても、組織の真の課題解決に繋がる価値あるデータを得ることはできません。
また、調査対象者の選定を誤ると、組織全体の傾向を正確に代表していない結果となったり、特定の部署や階層の声だけが過度に反映されたりする偏りが生じる可能性があるため、注意深い検討が必要です。
例えば、「中堅社員のリーダーシップ開発支援」がサーベイの目的ならば、対象者には中堅社員自身とその部下である従業員を含め、質問項目には「上司からのフィードバックの質と頻度」「目標設定の適切性と納得感」「チーム内コミュニケーションの円滑さ」など、リーダーシップやマネジメントスキルに関連する具体的な内容を盛り込むことが効果的です。
全従業員を対象とする大規模なサーベイの場合でも、部署、役職、勤続年数、年齢層といった属性情報を回答項目に加えることで、後の分析段階で層別の課題や傾向をより詳細に把握しやすくなります。
3.従業員へ事前説明を行い、心理的安全性を確保する
エンゲージメントサーベイを成功に導き、従業員から正直で質の高い回答を引き出すためには、サーベイ実施前に、その目的、意義、回答の匿名性が厳格に守られることなどを従業員に対して丁寧に説明し、安心して本音で回答できる心理的に安全な環境を醸成することが極めて不可欠です。
なぜなら、従業員がサーベイに対して何らかの不信感や、「自分の回答が特定されて人事評価に不利に影響するのではないか」といった強い不安を抱いたままでは、当たり障りのない回答や建前だけの意見に終始してしまい、サーベイから得られるデータの信頼性や有効性が著しく損なわれてしまうからです。
特に、組織の運営方法や直属の上司への意見など、ネガティブな内容やデリケートなトピックに関する率直なフィードバックは、従業員が報復を恐れることなく安心して発言できるという確信がなければ、決して得られることはありません。
サーベイ実施の数週間前から社内イントラネットや全従業員向けの説明会などを通じて、「このサーベイは、皆さんの職場環境をよりよくするためのものであり、個々人の評価とは一切関連付けられることはありません」といった情報を、経営トップからのメッセージと共に繰り返し明確に伝えることが有効です。
【関連コンテンツ】
4.サーベイを実施し、集計・分析する
事前の周到な計画と従業員への丁寧な説明という準備段階を経て、次に行うべきは、計画通りにスムーズにエンゲージメントサーベイを実施し、収集された回答データを客観的かつ多角的な視点から集計・分析することです。
このステップが、次の具体的な改善アクションに繋がる有益な洞察を得るための鍵となります。サーベイの実施方法が従業員にとって煩雑であったり、回答期間の設定が不適切であったりすると、回答率の低下や回答の質の劣化を招く可能性があります。
また、集計・分析のプロセスが表面的であったり、データの解釈に誤りがあったりすると、組織が抱える問題の本質を見誤り、結果として効果の薄い、あるいは的外れな改善施策につながってしまう危険性があるため、慎重な対応が求められます。
サーベイの実施にあたっては、多くの企業で導入されているオンラインのサーベイツールなどを活用し、従業員が自身のPCやスマートフォンから、時間や場所を選ばずに容易に回答できる環境を整備することが望ましいでしょう。
収集されたデータは、まず全体の平均スコアや傾向を把握し、次に部署別、役職別などの属性ごとにクロス集計を行い、特定の従業員グループに課題が集中していないかなどを詳細に分析します。
【関連コンテンツ】
5.結果を共有し、フィードバックを行う
エンゲージメントサーベイで収集・分析された結果は、経営層や管理職といった一部の関係者だけではなく、調査に協力した全従業員に対しても透明性を持って共有し、その内容について建設的なフィードバックや意見交換を行う機会を設けることが、組織の信頼関係を深め、全社的な改善活動への当事者意識を高める上で不可欠です。
従業員は、自分たちが提供した声が組織によってどのように受け止められ、会社がどのような課題を認識したのかを知る権利と強い関心を持っています。サーベイ結果の共有や、それに対する組織からのフィードバックが十分に行われなければ、従業員は「結局、自分たちの意見は聞いてもらえなかった」「アンケートに答えても何も変わらない」といった不信感や諦めの気持ちを抱き、エンゲージメントサーベイの意義そのものが失われてしまうからです。
例えば、サーベイの分析結果が出た後、速やかに全社集会などを開催し、社長自らが調査結果の概要を全従業員に向けて説明することが考えられます。
さらに、各部門においては、それぞれの管理職が自チームのより詳細な結果をメンバーと共有し、その結果に対するメンバーの感想や、具体的な改善アイデアについて自由に話し合うフィードバックセッションの時間を設けることも有効な取り組みです。
【関連コンテンツ】
6.改善アクションを具体化・実行する
エンゲージメントサーベイのプロセスにおける最終的なステップは、調査データの分析と従業員からのフィードバックを通じて明らかになった組織の課題に対し、具体的な改善アクションプランを策定し、それを組織全体で一丸となって着実に実行していくことです。
サーベイを実施し、現状の課題を詳細に特定しただけでは、組織が良い方向に変わることはありません。具体的な行動が伴ってはじめて、従業員はサーベイの真の意義を実感し、エンゲージメントの向上や組織文化の改善といった目に見える成果が生まれるのです。「調査はしたが、その後何も行動に移されない」という状況は、従業員の信頼を最も大きく損ねる行為であり、サーベイを「意味のないもの」にしてしまう最大の要因といっても過言ではありません。
例えば、「若手社員がキャリア成長の機会不足を感じている」という課題が主要なものとして特定された場合、「若手社員向けの新しい研修プログラムを3ヶ月以内に開発・導入する」といった、具体的で実行可能なアクションプランを策定します。各アクションには、明確な担当部署、具体的な実施期限、期待される成果を設定することが重要です。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントサーベイを無駄にしない5つの活用方法
ここでは、エンゲージメントサーベイの結果を「意味のあるもの」に変え、組織改善に確実に繋げるための具体的な活用方法を5つのポイントに絞って解説します。
エンゲージメントサーベイから得られた貴重なデータを最大限に活かし、組織の成長を促進するためには、以下の活用方法が考えられます。
<エンゲージメントサーベイを無駄にしない5つの活用方法>
収集したサーベイ結果を分かりやすく「見える化」し、組織が抱える本質的な課題を明確に特定する
全体傾向だけでなく、部門や階層ごとの特徴を詳細に分析し、きめ細やかな対策を講じる
サーベイ結果に基づき、従業員と直接対話するフィードバックセッションの機会を設ける
明らかになった課題に対し、具体的な改善アクションプランを策定し、迅速に実行に移す
実行したアクションの効果を定期的に測定し、その結果を次回のサーベイ設計や改善活動に活かす
調査結果を見える化し、課題を明確にする
エンゲージメントサーベイを無駄にしないための第一歩は、集められた多くの調査結果を、誰にでもわかりやすい形に見える化し、組織が本当に向き合うべき課題を客観的かつ明確に特定することです。
サーベイから得られる数値データや自由記述のコメントは、そのままでは情報量が膨大で、どこに本質的な問題が潜んでいるのか、どの課題から優先的に手をつけるべきかを見極めるのが難しい場合があります。見える化という工程を経ることで、組織全体のエンゲージメントの傾向、特に注意が必要な項目、さらには従業員の感情の分布などを直感的に理解できるようになります。
これにより、関係者間での課題認識の共有がスムーズに進み、データにもとづいた客観的な優先順位付けが格段に行いやすくなります。
たとえば、エンゲージメント全体のスコアだけでなく、「仕事のやりがい」「上司からの支援」「成長機会」といった個別の診断項目ごとの平均点をレーダーチャートで表示したり、部署ごとのスコアを比較したりすることで、自社の強みと弱みを一目で把握できます。
また、AIなどを活用したテキストマイニングで自由記述回答を分析し、頻出する単語や関連性の高いキーワードをクラウド形式で表示することも、従業員の関心事や不満のポイントを視覚的に捉えるのに有効です。
【関連コンテンツ】
部門ごとの傾向を分析し、ピンポイントで対策する
エンゲージメントサーベイの結果を組織全体で平均的に見るだけでは、重要な課題を見落としてしまう可能性があります。
サーベイを真に有効活用するためには、部門別、役職別、勤続年数別、あるいは年齢層別といったさまざまな属性ごとに結果を詳細に分析し、それぞれのグループが持つ特有の傾向や課題に合わせた、きめ細やかで具体的な対策を講じることが非常に重要です。
なぜなら、会社全体のエンゲージメントスコアが一見良好に見えたとしても、その内訳を詳しく調べてみると、特定の部門や階層では深刻な問題を抱えているというケースは決して珍しくないからです。全社平均の数値だけでは見過ごされてしまいがちな、局所的な課題や隠れた問題点を正確に特定し、それに対して効果的な改善策を打つためには、このようなセグメント別の詳細な分析アプローチが不可欠となります。
例えば、全社的なスコアに大きな変動がなくても、特定の技術部門や若手社員層で「成長機会への満足度」や「上司からのフィードバックの質」に関するスコアが著しく低いことが判明すれば、全社一律の施策ではなく、当該部門や層に特化した研修プログラムの新設やメンター制度の導入といった、よりピンポイントで効果的な対策を実施できます。
従業員とのフィードバックセッションを設ける
エンゲージメントサーベイの結果をもとに、分析された情報を一方的に従業員へ伝達するだけで終わらせるのではなく、サーベイ結果に対する従業員自身の率直な所感や具体的な改善アイデアについて直接対話し、意見を共有する「フィードバックセッション」を設けることは、サーベイを真に組織改善へと活用し、従業員と組織との間の信頼関係を強化するうえで効果的な手法です。
このような対話の場を通じて、従業員は自分たちの声が真剣に受け止められ、組織運営や職場環境の改善プロセスに主体的に関与しているという実感を持つことができます。これにより、組織改善への当事者意識が自然と高まり、より前向きな協力が得られやすくなります。
また、企業側にとっても、サーベイ結果の数値データだけでは見えてこない、課題の具体的な背景や、現場の従業員ならではの斬新で実用的な解決策のヒントが得られる貴重な機会となります。
たとえば、全社的な結果報告の後、各部署で管理職がファシリテーターとなり、チームメンバーとサーベイ結果を共有するミーティングを実施し、「この結果についてどう思うか?」「私たちのチームで改善できることは何か?」といったテーマで率直な意見交換を行うことで、ボトムアップでの改善提案の活発化を期待できます。
【関連コンテンツ】
改善アクションに落とし込み、すぐ実行に移す
エンゲージメントサーベイから得られた貴重な洞察や明確になった課題認識を、具体的な改善アクションプランへと迅速に転換し、組織全体で速やかに実行に移すことがサーベイを「意味のある投資」とし、実際の組織改善を実現するための重要な活用方法です。
どれほど詳細で的確な分析を行い、組織が抱える本質的な課題を発見できたとしても、それが具体的な行動に繋がらなければ、組織は何も変わることはありません。従業員は、自分たちがサーベイを通じて発信した声が、目に見える形での変化や改善に結びつくことを強く期待しています。
「調査はしたが、その後何も具体的な動きがない」という状況は、従業員の信頼を著しく損ない、エンゲージメントを向上させるどころか、むしろ低下させてしまう要因となるからです。
たとえば、サーベイで「若手社員の成長機会の不足」が課題として明確になった場合、「メンター制度の導入を3ヶ月以内に開始する」「資格取得支援制度の予算を次年度から倍増する」といった、担当部署、期限、具体的な目標を伴うアクションプランを策定し、速やかに実行に移します。
たとえ小さな改善であっても、迅速に着手し、その進捗を共有することが、従業員の信頼を高める鍵です。
アクションの効果を測定し、再サーベイに活かす
エンゲージメントサーベイを無駄にせず、組織の持続的な成長につなげるための重要な活用方法は、継続的な改善サイクルを確立することです。
一度のアクションや施策で組織の全ての課題が完全に解決することは稀であり、また、外部環境の変化や組織内部の動きによって、従業員の意識や組織が抱える課題は常に変化し続けるものです。
実施した施策の効果を客観的に測定し、その有効性を検証することで、必要に応じて改善策の軌道修正を行い、より効果的で効率的なエンゲージメント向上へとつなげていくことができます。たとえば、コミュニケーション活性化のために新しい会議形式を導入した後、数ヶ月後に短いパルスサーベイを実施し、情報共有の満足度に関する項目を重点的に測定します。
その結果をもとに、会議の運営方法を見直すといった改善を行います。また、年に一度実施するエンゲージメントサーベイでは、過去のサーベイ結果からの各項目のスコアの変化を詳細に見ることで、長期的な視点での施策の効果や、新たに出現してきた課題の兆候を早期に捉えることが可能です。
エンゲージメントサーベイを効果的に実施した3つの事例
ここでは、エンゲージメントサーベイを実際に活用し、組織改善に成功した企業の具体的な事例を3つ紹介します。これらの事例から、サーベイを成功に導くためのヒントや実践的なアプローチを学び取ることができます。
各社がどのような課題を持ち、エンゲージメントサーベイをどのように活用して成果につなげたのか、そのポイントを見ていきましょう。
<エンゲージメントサーベイを効果的に実施した3つの事例>
従業員に寄り添うサーベイ運用。 2,000名規模の組織改善の取り組みとは
全社を巻き込むサーベイ運用。各部門が主体となって進める組織改善の仕組みとは
「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善
全社を巻き込むサーベイ運用。各部門が主体となって進める組織改善の仕組みとは
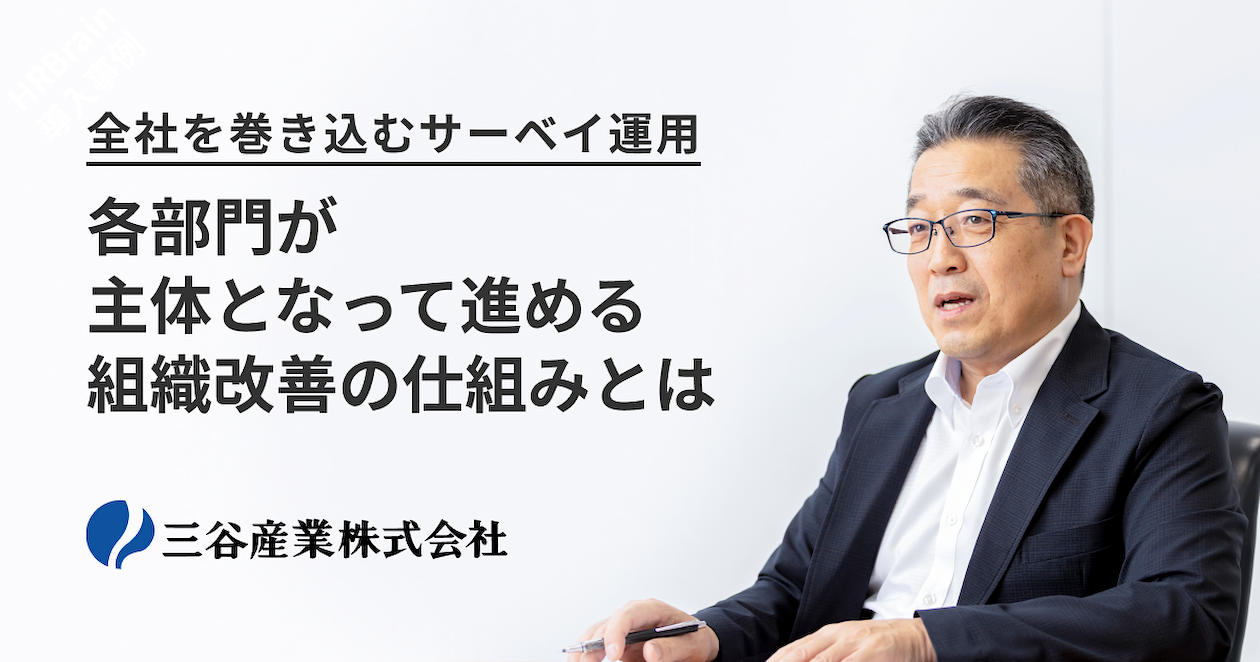
三谷産業株式会社では、従来の組織診断サーベイにおいて実施間隔の長さや集計の遅さ、運用の煩雑さに課題があり、人事部門の負担も大きく、改善活動の継続が困難でした。加えて、社員エンゲージメントが非財務的な経営目標として注目されたことで、より実態を把握できる仕組みが求められていました。
この背景を受け、同社は2019年から利用しているHRBrainに加え、組織診断サーベイ「EX Intelligence」を導入。期待と実感のギャップを数値化できる点や設問の柔軟な設計、データ分析の多軸性が評価されました。特に「自分がどうありたいか」といった視点で設問を設計できる点が、部門ごとの理解を促し、主体的な改善行動を後押ししました。
分析は各部門が担い、1on1や経営会議での共有を通じて、トップダウンとボトムアップの両輪で改善体制を整備。その結果、サーベイスコアは3.3ポイント向上し、施策の即時実行と人事負担の軽減、全社を巻き込んだ改善サイクルの定着が進みました。現在では、部門主導の自律的運用体制が確立され、持続的なエンゲージメント向上に取り組んでいます。
【関連コンテンツ】
「サーベイ結果が出たら終わり」ではなくその先へ。HRBrainと二人三脚で進める組織改善

東レ株式会社では、従来の従業員サーベイが組織改善につながらず、結果の分析が難しくフィードバックまでに半年かかるスピード面の問題がありました。サーベイ内容が従業員のキャリア観に追いついておらず、マネージャー層が結果を活用できない状況も続いていました。改善には自律的な現場の動きと迅速なフィードバックが求められていました。
こうした課題に対応するため、2023年にEX Intelligenceを導入し、「期待」と「実感」のギャップを可視化、組織の優先課題を把握できる点が評価されました。結果を即日閲覧可能にし、迅速な現場アクションを促進しました。UIの分かりやすさや支援ツール、コンサルタントのサポートも活用を後押ししました。サーベイ頻度も2年に1回から年1回に見直されました。
導入後、各部署で組織改善のアクションプランが策定され実行されています。工場単位でキャリア研修や懇話会が開催され、現場主導の改善が進みました。経営層や現場のライン長の関心が高まり、サーベイ結果が全社で共有されています。従業員から「経営や人事が本気で向き合っている」との声が上がり改善が進んでいます。今後、人的資本開示やPRを視野に入れ取り組みを深化させる方針です。
【関連コンテンツ】
おすすめのエンゲージメントサーベイ実施ツール「HRBrain」

エンゲージメント経営の成功には、現状の把握と継続的な改善が欠かせません。その鍵となるのが「エンゲージメントサーベイ」です。中でもおすすめなのが、人的資本経営や従業員エンゲージメントの向上を支援する「HRBrain 組織診断サーベイ」です。
HRBrainは、組織の課題を可視化するだけでなく、部署別・職種別といった多角的な分析機能により、現場ごとの具体的な打ち手を検討する際にも非常に有効です。また、エンゲージメントスコアや関連指標を定点観測できるため、取り組みの成果を定量的に確認しながら改善を進められるのも大きな特徴です。
初めてサーベイを導入する企業でも活用しやすい設計になっており、「まずは小さくはじめて、成果を見ながら展開したい」といった企業にも適しています。組織のエンゲージメント向上に本気で取り組む企業にとって、HRBrainは心強いパートナーとなるでしょう。
エンゲージメントサーベイを「意味ない」で終わらせず、組織改善に活かしましょう
エンゲージメントサーベイが「意味ない」と感じるのは、正しく活用できていないことが原因かもしれません。
目的が不明確なまま実施されたり、調査後に何も変化がなければ、従業員は無駄な調査と捉えてしまいます。しかし、設計・実施・分析・改善という一連のプロセスを丁寧に行えば、サーベイは組織改革の起点になります。今こそ、自社のサーベイ運用を見直し、エンゲージメント向上の一歩を踏み出しましょう。







