エンゲージメントサーベイとは?実施する目的や導入手順を解説
組織状態の把握から分析・課題抽出までワンストップで実現
- エンゲージメントサーベイとは
- エンゲージメントサーベイとその他のサーベイの違い
- 組織サーベイとの違い
- 従業員サーベイとの違い
- モラールサーベイとの違い
- パルスサーベイとの違い
- 従業員満足度調査との違い
- エンゲージメントサーベイを実施する4つの目的
- 組織課題を可視化する
- 従業員と企業とのギャップを把握する
- データを人事施策に活かす
- データをチーム運営に活かす
- エンゲージメントサーベイを実施する6つのメリット
- 組織やチームの課題が明確になる
- 従業員のモチベーションを維持・向上できる
- 従業員の離職率低下につながる
- 生産性や業績の向上が期待できる
- リファラル採用を活性化できる
- 人事トラブルを防止しやすくなる
- エンゲージメントサーベイの2つのデメリット・注意点
- 結果を活かせないと従業員の不信感につながる
- 現場の業務負担が増加してしまう
- エンゲージメントサーベイの代表的な調査方法と質問項目例
- Q12(キュートゥエルブ)
- ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)
- 一般性セルフ・エフィカシー(自己効力感)尺度(GSES)
- MBI-GS(マスラック・バーンアウト・インベントリー)
- エンゲージメントサーベイ導入から改善までの5ステップの手順
- 1.実施目的を明確に設定する
- 2.設問を設計し従業員へ周知する
- 3.秘匿性を担保してサーベイを実施する
- 4.結果を分析して課題を特定する
- 5.改善策を策定し実行に移す
- エンゲージメントサーベイの分析方法と活用のポイント
- サーベイ結果を読み解く
- エンゲージメント低下の「問題設定」を行う
- エンゲージメントに影響を及ぼす変数を見つける
- 分析結果をもとに施策を検討する
- 調査結果を従業員に必ずフィードバックする
- 調査を繰り返し行う
- エンゲージメントサーベイツールの選び方
- ツールを使用する目的を明確にしてツールを選ぶ
- 高度な分析ができ操作性がよいツールを選ぶ
- レポート機能があるツールを選ぶ
- エンゲージメントサーベイのおすすめツール「HRBrain 組織診断サーベイ」
- エンゲージメントサーベイツールの活用事例
- エンゲージメントサーベイを活用し、組織課題を解決する一歩を踏み出しましょう
エンゲージメントサーベイとは、従業員の視点からみた「会社とのつながりの強さ」を数値化して把握し改善するための調査ツールです。転職市場の活発化やテレワークの普及を背景に、離職防止や生産性向上への取り組みに注目が集まり、エンゲージメントサーベイが注目されるようになりました。
この記事では、エンゲージメントサーベイの意味や目的、メリット・デメリットなどを詳しく解説します。エンゲージメントサーベイの具体的な調査方法や質問項目や分析方法、導入事例なども紹介しているので、自社におけるエンゲージメントの状況を把握したい方はぜひ参考にしてみてください。
エンゲージメントサーベイとは
エンゲージメントサーベイとは、従業員の視点からみた「会社とのつながりの強さ」を数値化して把握し、改善するための調査ツールです。
会社と従業員とのつながりの強さを一般的には「従業員エンゲージメント」と表現することから、それを調査するツールとして、エンゲージメントサーベイと呼ばれています。
エンゲージメントサーベイでは、従業員が会社や仕事に対してどれだけ「ポジティブな感情を持っているのか」を測定できます。
従業員エンゲージメントの概要や従業員満足度との違いなどを詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事を参考にしてみてください。
▼「従業員エンゲージメント」についてさらに詳しく
エンゲージメントサーベイとその他のサーベイの違い
エンゲージメントサーベイは、以下のサーベイと混同される場合があるため、それぞれの目的や測定領域の観点から違いを解説します。
組織サーベイ
従業員サーベイ
モラールサーベイ
パルスサーベイ
従業員満足度調査
サーベイそれぞれの違いを理解することは、自社の課題解決に効果的な調査を正しく選定するための第一歩です。
組織サーベイとの違い
組織サーベイは、組織文化や業務プロセスの効率性など、企業の状態を多角的に把握するための調査の総称です。
これに対しエンゲージメントサーベイは、その中でも特に従業員の自発的な貢献意欲と、企業の業績との関連性に焦点を当てた調査と位置づけられます。
例えば「社内の情報共有は円滑か?」を問うのは広義の組織サーベイですが、「自身の仕事は会社の成功に貢献しているか?」を問うのがエンゲージメントサーベイです。
組織全体の健康診断として幅広いテーマを扱うのが組織サーベイ、その中でも人材を資本と捉え、業績向上につなげるための具体的な打ち手を発見する手段がエンゲージメントサーベイであると理解することが重要です。
【関連コンテンツ】
従業員サーベイとの違い
従業員サーベイも従業員を対象とした調査の総称であり、エンゲージメントサーベイはそのひとつです。ただし、エンゲージメントサーベイは、従業員の定着や貢献といった未来の行動を予測し、促進するという、より戦略的な意図を持っています。
一般的な従業員サーベイが現状の意見や要望を収集すること自体を目的とする一方、エンゲージメントサーベイは収集したデータを分析して課題の優先順位を決定し、具体的な改善アクションを通じて組織全体のパフォーマンス向上につなげることを前提に設計されています。
例えば「どのような福利厚生を望むか」という質問は現状把握が目的ですが、「この会社で働き続けたいか」という問いは、離職の先行指標として未来を探る視点です。
【関連コンテンツ】
モラールサーベイとの違い
モラールサーベイは、集団としての士気や労働意欲といった一時的な感情や雰囲気を測定する調査です。一方で、エンゲージメントサーベイは、個人と組織の間の持続的かつポジティブな心理状態を測定します。
モラール(意欲)は、短期的なプロジェクトの成功や繁忙期といった外部環境によって変動しやすい性質を持ちます。エンゲージメントは、仕事の意義や成長機会といった、より本質的な動機付け要因に根差しており、比較的安定した指標です。
例えば、一時的な業務負荷の増大でチームの意欲は低下しても、その業務に大きな成長機会を実感している従業員は、高いエンゲージメントを維持し、主体的に行動する可能性があります。
組織の短期的な雰囲気を知るにはモラールサーベイが有効ですが、企業の持続的成長のためには、エンゲージメントの測定が不可欠です。
【関連コンテンツ】
パルスサーベイとの違い
エンゲージメントサーベイが「何を測るか(測定内容)」を指すのに対し、パルスサーベイは「どのように測るか(測定頻度・形式)」を指すのが違いです。
両者は対立する概念ではなく、目的と手段の関係にあります。パルスサーベイは心臓の脈拍のように、短い間隔(毎週・毎月・四半期ごと)で、少ない設問数で定点観測する調査手法を指します。
この手法を用いて、エンゲージメントの状態をタイムリーに把握するのが一般的です。年1回、網羅的な設問で組織全体の課題を棚卸しするのがセンサスサーベイであり、その結果見つかった課題の改善策を実行し、効果を測るために毎月数問で定点観測するのがパルスサーベイです。
【関連リンク】
従業員満足度調査との違い
従業員満足度調査は、会社が従業員に与える給与や福利厚生、職場環境といった待遇への満足感を測る調査です。一方、エンゲージメントサーベイは、従業員が会社に対して自発的に貢献したいと思う貢献意欲を測定します。
満足度は、従業員が会社から受け取ることへの評価であり、受動的な状態です。満足度が高くても、必ずしも業績向上につながるとは限りません。「不満はないが、言われたことしかしない」社員を生む可能性もあります。
一方、エンゲージメントは、従業員と会社が相互に成長を目指す能動的な関係性であり、企業の生産性やイノベーションに直結します。
業績向上というゴールから逆算すると、施策のKPIにはエンゲージメント指標を主軸に据えることが、現代の組織運営において合理的といえるでしょう。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントサーベイを実施する4つの目的
エンゲージメントサーベイを実施するうえで、まずは実施の目的を明確にすることが大切です。
エンゲージメントサーベイを実施する、4つの目的について確認してみましょう。
<エンゲージメントサーベイを実施する目的>
- 組織課題を可視化する
- 従業員と企業とのギャップを把握する
- データを人事施策に活かす
- データをチーム運営に活かす
組織課題を可視化する
エンゲージメントサーベイを実施する目的の1つ目は、「組織課題を可視化する」ことです。
エンゲージメントサーベイを実施することで、本来数値化できない従業員のエンゲージメントを数値化やグラフ化し、可視化することができます。
エンゲージメントサーベイを定期的に行い、数値の変化を確認することで、従業員のモチベーションや、会社に対する愛着度の変化などを察知することができます。
【関連コンテンツ】
従業員と企業とのギャップを把握する
エンゲージメントサーベイを実施する目的の2つ目は、「従業員と企業とのギャップを把握する」ことです。
エンゲージメントサーベイを実施することで、従業員が企業や組織へ求める期待と現状とのギャップを把握することができます。
また、サーベイへの回答を通じて、従業員自身も上司・同僚との関係や自己成長に対する期待と現状の違いに気づくことができ、自己理解や意識の変化にもつながります。
データを人事施策に活かす
エンゲージメントサーベイを実施する目的の3つ目は、「データを人事施策に活かす」ことです。
エンゲージメントサーベイを実施することで、従業員の「モチベーション」「コミュニケーション」「マネジメント」などに対する、人事上の課題を発見し数値として明確に提示することができます。
エンゲージメントサーベイでの調査結果を分析し、「1on1ミーティングの実施」「評価制度の見直しや改善」「組織開発」「環境整備」などに活用することができます。
【関連コンテンツ】
データをチーム運営に活かす
エンゲージメントサーベイを実施する目的の4つ目は、「データをチーム運営に活かす」ことです。
エンゲージメントサーベイでの調査結果を、管理職に共有しチーム内で議論することで、企業や組織が抱える課題を、従業員ひとりひとりが「自分事」として考えることができるようになるため、ポジティブなコミュニケーションが増えたり、エンゲージメントにも良い影響を与えます。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントサーベイを実施する6つのメリット
エンゲージメントサーベイを実施することで得られるメリットには、どのようなものがあるのか、エンゲージメントサーベイを実施することで得られる、6つのメリットについて確認してみましょう。
<エンゲージメントサーベイのメリット>
- 組織やチームの課題が明確になる
- 従業員のモチベーションを維持・向上できる
- 従業員の離職率低下につながる
- 生産性や業績の向上が期待できる
- リファラル採用を活性化できる
- 人事トラブルを防止しやすくなる
組織やチームの課題が明確になる
エンゲージメントサーベイを実施するメリットの1つ目は、これまで「肌感覚」でしか捉えられなかった課題を、客観的なデータで特定できることです。
サーベイは組織の精密検査として機能し、部署・役職・勤続年数などの属性別データを分析することで、どの層にどのような課題があるかを明確にします。
例えば「社内の風通しが悪い」という漠然とした問題が「A事業部では部署間の連携不足、B事業部では上司からのフィードバック不足がエンゲージメントを阻害している」というように、解像度高く分解されます。
課題が明確になることは全ての改善活動の出発点です。データという共通言語を持つことで、感覚的な議論を排し、組織全体で的を射たアクションプランの策定と実行にスムーズに移行できます。
従業員のモチベーションを維持・向上できる
エンゲージメントサーベイを実施するメリットの2つ目は、「モチベーションの維持と向上」です。
働き方の多様化や、テレワークの普及によって、対面でのコミュニケーションが減り、従業員一人ひとりの状態を把握することが難しくなっています。
エンゲージメントサーベイを定期的に実施することで、従業員のモチベーションの変化や、チームのコンディションを可視化できます。
そのため、テレワークでのコミュニケーション不足や孤独感、異動などの環境の変化によるモチベーションの低下など、従業員のコンディションの変化を察知することが可能です。
また、エンゲージメントサーベイのスコアによって、従業員のモチベーションに変化が見られた際は、1on1ミーティングや人事面談などの適切なフォローを行い、モチベーションの維持や向上に向けた対策を実施できます。
【関連コンテンツ】
従業員の離職率低下につながる
エンゲージメントサーベイを実施するメリットの3つ目は、離職率の低下です。
サーベイの結果をもとに、エンゲージメント向上に向けた施策を実施することで、従業員の会社やチームへの帰属意識が高まり、離職を防ぐ効果が期待できます。
さらに、エンゲージメントサーベイを活用することで、従業員の「離職の予兆」を早期に発見することも可能です。
それにより、これまで育成してきた従業員や、高い業績を残してきた従業員、幹部候補の従業員などが、突然退職する、「びっくり退職」を防ぐこともできるでしょう。
離職の予兆を見逃さないためにも、エンゲージメントサーベイの実施を定期的に行うことが大切です。
エンゲージメントサーベイの結果から、従業員に離職の予兆が見られた場合は、人事面談を実施するなど、適切なフォローを行うことで、離職率の低下につなげることができるでしょう。
【関連コンテンツ】
生産性や業績の向上が期待できる
エンゲージメントサーベイを実施するメリットの4つ目は、生産性や業績の向上です。
エンゲージメントサーベイの結果をもとに、以下のような施策を行うことで、従業員が働きがいを感じ、生産性の向上を期待できます。
人事施策の見直しの実施
課題解決に向けた施策の実施
コミュニケーション方法の見直し
適材適所の人事配置
得意領域への異動
さらに、生産性が高まることで、質のよいサービスや商品が生まれやすくなり、企業としての利益が増え、業績向上につながっていくでしょう。
【関連コンテンツ】
リファラル採用を活性化できる
エンゲージメントサーベイを実施するメリットの5つ目は、リファラル採用の活性化です。
リファラル採用とは、自社の従業員の紹介によって、人材を採用する手法です。従業員が、自社の求めるスキルや人物像に合った人材を紹介することで、信頼性の高い採用が可能になります。
また、エンゲージメントの高い従業員と似た人材を採用することができる可能性があるため、企業とのマッチング精度が上がり、人員確保の効果が一層高まります。
エンゲージメントサーベイを通じて従業員の意欲や満足度を高めることが、リファラル採用の促進と採用成果の向上に直結するのです。
【関連コンテンツ】
人事トラブルを防止しやすくなる
エンゲージメントサーベイを実施するメリットの6つ目は、人事トラブルの防止です。
エンゲージメントサーベイの質問や設計にもよりますが、企業や組織内で発生する、人事トラブルの予兆を発見できます。
人間関係でのトラブルや、パワハラ、セクハラなど、なかなか上司や同僚に相談できない悩みを打ち明けられます。
そのため、サーベイを実施する際には、以下の2つが非常に重要です。
調査結果の取り扱いを周知すること
自由記述(フリーコメント)欄を設けること
また、エンゲージメントサーベイの調査結果から、人事トラブルを発見し、調査を行う場合は、必ず「守秘すること」「信頼性を損なうようなことをしないこと」に気をつけるようにしましょう。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントサーベイの2つのデメリット・注意点
ここでは、エンゲージメントサーベイを導入・運用する上で避けては通れない2つのデメリットと、その対策について解説します。
これらの注意点を事前に理解し、対策を織り込んで計画することが、サーベイを成功に導く上で極めて重要です。
<エンゲージメントサーベイの2つのデメリット・注意点>
結果を活かせないと従業員の不信感につながる
現場の業務負担が増加してしまう
結果を活かせないと従業員の不信感につながる
エンゲージメントサーベイを実施したのに何のアクションも起こさないことは、従業員が不信感を感じる原因のひとつです。
従業員は、忙しい中でも「自分たちの声で会社を良くできるかもしれない」という期待を込めて回答しています。
しかし、サーベイ後に結果の共有や改善活動が行われないと、「結局、声を聞くだけで何も変わらない」と感じ、会社への信頼を失ってしまいます。
一度でも「回答しても無駄だった」という経験をすると、次回のサーベイでは回答率が著しく低下します。
この事態を避けるため、サーベイ実施前に結果の共有と改善アクションの実行を必ず約束し、その体制を整えておくことが重要です。
現場の業務負担が増加してしまう
エンゲージメントサーベイは、回答する従業員だけでなく、結果を受けて改善アクションを担う現場の管理職の業務負担を増加させるという側面を持ちます。
サーベイの効果を最大化するには、結果の分析、チームでの対話、アクションプランの策定・実行といったプロセスが欠かせません。
これらはすべて既存業務に追加されるため、多忙なマネージャーにとって大きな負担となり、結果的に取り組みが形骸化してしまうこともあるでしょう。
対策としては、以下のような現場支援の仕組みが有効です。
人事部が要点をまとめたレポートを提供し、分析の手間を軽減する
チーム対話用の進行表や質問例を用意し、ミーティングの準備を簡略化する
部署ごとに取り組む課題を1~2個に絞るなど、明確な優先順位を示す
このように、負担を最小限に抑える工夫をすることで、マネージャーが無理なく継続的に改善活動に取り組める環境を整えられます。
エンゲージメントサーベイの代表的な調査方法と質問項目例
エンゲージメントサーベイは、実際にどのような質問項目で調査するか、エンゲージメントサーベイの質問項目の参考例について、代表的な4つの調査の質問項目について確認してみましょう。
<エンゲージメントサーベイの代表的な調査方法>
Q12(キュートゥエルブ)
ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)
一般性セルフ・エフィカシー(自己効力感)尺度(GSES)
MBI-GS(マスラック・バーンアウト・インベントリー)
Q12(キュートゥエルブ)
Q12(キュートゥエルブ)は、米ギャラップ社がアメリカの心理学者フランク・L・シュミット博士とともに開発したエンゲージメントサーベイです。
従業員に対して、全世界1,300万人を調査し導きだした「12の質問」を行うことで、従業員のエンゲージメントを測定します。
実際に「12の質問」がどのようなものなのか、確認してみましょう。
【12の質問】
分類 | No | 設問内容 |
|---|---|---|
仕事をするための基本事項である、動機や環境が整っているか | Q01 | 職場で自分が何を期待されているのかを知っている |
Q02 | 仕事をうまく行うために必要な材料や道具を与えられている | |
仕事への貢献度や、周囲にどう評価されているか | Q03 | 職場で最も得意なことをする機会を毎日与えられている |
Q04 | この1週間のうちに、よい仕事をしたと認められたり、褒められたりした | |
Q05 | 上司または職場の誰かが、自分をひとりの人間として気にかけてくれている | |
Q06 | 職場の誰かが自分の成長を促してくれる | |
「職場」への帰属意識と、同僚への信頼感 | Q07 | 職場で自分の意見が尊重されているようだ |
Q08 | 会社の使命や目的が、自分の仕事は重要だと感じさせてくれる | |
Q09 | 職場の同僚が真剣に質の高い仕事をしようとしている | |
Q10 | 職場に親友がいる | |
「職場」での自身の成長性や、発展への意識 | Q11 | この6カ月のうちに、職場の誰かが自分の進歩について話してくれた |
Q12 | この1年のうちに、仕事について学び、成長する機会があった |
「12の質問」に対して、回答は以下の5つの選択肢から行います。回答の点数を合計して、平均スコアを計算します。
完全にあてはまる(5点)
ややあてはまる(4点)
どちらともいえない(3点)
やや当てはまらない(2点)
完全に当てはまらない(1点)
平均点は「3.6点」で、「3.8点以上」はエンゲージメントが高め、「3.2以下」は要注意となっています。
(参考)Gallup「Who's Responsible for Employee Engagement」
【参考記事】
ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)
ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)は、国際的に信頼性と妥当性が検証されているエンゲージメント尺度の1つです。
UWESでは、ワークエンゲージメントを以下3つの要素から評価します。
要素 | 詳細 |
|---|---|
活力(Vigor) | 仕事へのエネルギーや粘り強さ |
熱意(Dedication) | 仕事への誇りややりがい |
没頭(Absorption) | 仕事への集中や夢中になる状態 |
ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)の設問は、日本語版では、17項目と、短縮版の9項目、3項目の3種類があります。具体的な内容は以下の表です。
17項目版
No. | 項目 | カテゴリ |
|---|---|---|
1 | 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる | 活力 |
2 | 自分の仕事に、意義や価値を大いに感じる | 熱意 |
3 | 仕事をしていると、時間がたつのが速い | 没頭 |
4 | 職場では、元気が出て精力的になるように感じる | 活力 |
5 | 仕事に熱心である | 熱意 |
6 | 仕事をしていると、他のことはすべて忘れてしまう | 没頭 |
7 | 仕事は、私に活力を与えてくれる | 熱意 |
8 | 朝に目がさめると、さあ仕事へ行こう、という気持ちになる | 活力 |
9 | 仕事に没頭しているとき、幸せだと感じる | 没頭 |
10 | 自分の仕事に誇りを感じる | 熱意 |
11 | 私は仕事にのめり込んでいる | 没頭 |
12 | 長時間休まずに、働き続けることができる | 活力 |
13 | 私にとって仕事は、意欲をかきたてるものである | 熱意 |
14 | 仕事をしていると、つい夢中になってしまう | 没頭 |
15 | 職場では、気持ちがはつらつとしている | 活力 |
16 | 仕事から頭を切り離すのが難しい | 没頭 |
17 | ことがうまく運んでいないときでも、幸福感をもって仕事をする | 活力 |
(参考:ワーク・エンゲイジメント(UWES)|慶應義塾大学総合政策学部島津研究室)
9項目版
No. | 項目 | カテゴリ |
|---|---|---|
1 | 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる | 活力 |
2 | 職場では、元気が出て精力的になるように感じる | 活力 |
3 | 仕事に熱心である | 熱意 |
4 | 仕事は、私に活力を与えてくれる | 熱意 |
5 | 朝に目がさめると、さあ仕事へ行こう、という気持ちになる | 活力 |
6 | 仕事に没頭しているとき、幸せだと感じる | 没頭 |
7 | 自分の仕事に誇りを感じる | 熱意 |
8 | 私は仕事にのめり込んでいる | 没頭 |
9 | 仕事をしていると、つい夢中になってしまう | 没頭 |
(参考:ワーク・エンゲイジメント(UWES)|慶應義塾大学総合政策学部島津研究室)
3項目版
No. | 項目 | カテゴリ |
|---|---|---|
1 | 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる | 活力 |
2 | 仕事に熱心である | 熱意 |
3 | 私は仕事にのめり込んでいる | 没頭 |
(参考:ワーク・エンゲイジメント(UWES)|慶應義塾大学総合政策学部島津研究室)
ワーク・エンゲージメント尺度(UWES)は、エンゲージメントの考え方の基本的な概念であるため、関連する論文を読めばエンゲージメント調査の設問設定の参考として、大いに役立ちます。
【参考記事】
一般性セルフ・エフィカシー(自己効力感)尺度(GSES)
一般性セルフ・エフィカシー(自己効力感)尺度(GSES)は、「自己効力感」を測定する尺度として最も一般的な測定尺度です。
自己効力感とは、「自分はできる」という感覚を指し、GSESはこの「できる」という感覚を測定します。
GSESスコアが高いほど自己効力感が高く活動的であり、スコアが低いほど自己効力感が低くパフォーマンスが低下している可能性があります。
GSESは、もともとはうつ状態に対する医療現場での使用を想定して作られました。そのためスコアが10点未満の被験者には、何らかの抑うつ傾向がみられる可能性があります。
組織パフォーマンスの状態を調べるとともに、メンタル不調者を見つけることができる優れた測定尺度です。
具体的な質問項目は以下です。
No. | 因子 | No. | 項目 |
|---|---|---|---|
1 | 行動の積極性 | 1-1 | 何か仕事をするときは、自信を持ってやるほうである |
1-2 | 人と比べて心配性なほうである | ||
1-3 | 何ごとがあっても、迷わず決定するほうである | ||
1-4 | ひっこみじあんなほうだと思う | ||
1-5 | 結果の見通しがつかない仕事でも、積極的にとりくむほうだと思う | ||
1-6 | なんにでも積極的にとりくむほうである | ||
1-7 | 積極的に活動するのは、苦手なほうである | ||
2 | 失敗に対する不安 | 2-1 | 過去に犯した失敗や過ちを思いだすと、暗い気持ちになることがある |
2-2 | 仕事を終えた後、失敗したと感じることのほうが多い | ||
2-3 | 何かをするとき、うまくゆかないのではないかと不安になることが多い | ||
2-4 | どうやったらよいか決心のつかずに仕事にとりかかれないことがある | ||
2-5 | 小さな失敗でも人よりずっと気にするほうである | ||
3 | 能力の社会的位置付け | 3-1 | 友人より優れた能力がある |
3-2 | 人より器用なほうである | ||
3-3 | 友人よりも特に優れている知識を持っている分野がある | ||
3-4 | 世の中に貢献できる力があると思う |
(参考)J-STAGE「一般性セルフ・エフィカシー尺度作成の試み(原著論文)」から作成
【参考記事】
MBI-GS(マスラック・バーンアウト・インベントリー)
MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)は、エンゲージメントの対極にある概念、「バーンアウト(燃え尽き症候群)」を測定するための世界標準の尺度です。
バーンアウトは、深刻な生産性の低下、メンタルヘルスの問題、離職の直接的な原因となります。
エンゲージメントというポジティブな側面だけでなく、バーンアウトというネガティブな側面を同時に測定することで、組織の健康状態をより正確に診断し、深刻なリスクを未然に防ぎやすくなります。
以下が質問項目の例です。
要素 | 質問例 |
|---|---|
情緒的消耗感 | 仕事で心身ともに疲れ果てた |
シニシズム | 仕事への熱意が失われた |
個人的達成感 | 自分は今の仕事で大きな成果をあげている |
【参考記事】
エンゲージメントサーベイ導入から改善までの5ステップの手順
ここでは、エンゲージメントサーベイを調査だけで終わらせず、確実に組織改善につなげるための具体的な5つのステップを解説します。
以下の手順に沿って計画的に進めることが、サーベイを成功させる鍵になるため、ぜひ実践の参考にしてみてください。
<エンゲージメントサーベイ導入から改善までの5ステップの手順>
- 実施目的を明確に設定する
- 設問を設計し従業員へ周知する
- 秘匿性を担保してサーベイを実施する
- 結果を分析して課題を特定する
- 改善策を策定し実行に移す
1.実施目的を明確に設定する
最初のステップは、「エンゲージメントサーベイを通じて何を達成したいのか」という目的を具体的かつ明確に設定することです。
目的が曖昧では集めるべきデータが定まらず、結果の解釈も散漫になります。「若手層の離職率低下」「マネジメント層の育成」など、具体的な経営・人事課題と結びつけることでサーベイの価値は高まります。
例えば「中堅社員の離職率の高さを課題とし、その要因を特定してリテンション施策に活かす」といった目的を設定します。
サーベイを計画する際は、まず経営陣や人事を巻き込み、解決したい組織課題と目的の合意形成を行いましょう。
2.設問を設計し従業員へ周知する
設定した目的に基づいて、回答者の負担を考慮した設問を設計し、サーベイの意図や匿名性の担保について全従業員へ丁寧に事前周知することが重要です。設問の質と従業員の協力姿勢が、データの信頼性を左右します。
長すぎる設問は回答の質を下げ、目的や匿名性への不信感は回答率の低下に直結します。「なぜ答えるのか」「答えても安全なのか」という従業員の不安を払拭することが不可欠です。
設問数は10分以内で回答できる18〜35問を目安とし、尺度は5〜7段階のリッカート方式が一般的です。
周知の際は、経営トップから「結果を必ず改善に活かす」というメッセージを発信し、回答結果の取り扱いを明確に伝えましょう。
3.秘匿性を担保してサーベイを実施する
従業員が本音で回答できるよう、個人の特定につながらない秘匿性を技術的・制度的に担保した上でサーベイを実施することが重要です。
「誰が回答したかばれるのではないか」「人事評価に影響するのでは」という不安は、正直な回答を妨げる要因です。ネガティブな意見ほど、安心して発言できる環境がなければ集まりません。
従業員が直感的に回答できるように、秘匿性の担保やプライバシーへの配慮などを行なったうえで、エンゲージメントサーベイを実施しましょう。
4.結果を分析して課題を特定する
エンゲージメントサーベイで収集したデータは、単にスコアの低い項目を見るだけでなく、エンゲージメント全体への影響度が最も高い要因を特定することが重要です。よくある失敗は、スコアが低いというだけで影響の小さい問題にリソースを割いてしまうことです。
限られたリソースで効果的な改善を行うには、どの課題がエンゲージメント低下の根本原因に近いかを見極める必要があります。
収集した調査結果を表面的なデータとして捉えるのではなく、データをもとに課題を分析し、組織課題やエンゲージメントに影響している要因を見つけましょう。
5.改善策を策定し実行に移す
分析で特定した最優先課題に対し、具体的な改善アクションプランを策定し、責任者と期限を明確にして実行に移します。
そして、その進捗と結果を従業員に必ずフィードバックします。分析だけで終わらせては、従業員の不信感を招くリスクが高いため、結果をもとにしたアクションプランを実行し、振り返りを欠かさず行いましょう。
「調査結果が具体的な変化につながった」と従業員が実感してはじめて、エンゲージメントサーベイは成功したといえます。
エンゲージメントサーベイの分析方法と活用のポイント
エンゲージメントサーベイを実施してみたものの、エンゲージメントサーベイで収集したデータの分析方法や活用に悩んでいる場合もあるかもしれません。
エンゲージメントサーベイで収集したデータの分析方法と活用について、6つのステップに分けて確認してみましょう。
<エンゲージメントサーベイの分析方法と活用>
- サーベイ結果を読み解く
- エンゲージメント低下の「問題設定」を行う
- エンゲージメントに影響を及ぼす変数を見つける
- 分析結果をもとに施策を検討する
- 調査結果を従業員に必ずフィードバックする
- エンゲージメントサーベイでの調査を繰り返し行う
サーベイ結果を読み解く
エンゲージメントサーベイで収集したデータの分析方法と活用のステップの1つ目は、「サーベイ結果を読み解く」ことです。
エンゲージメントサーベイの結果自体は重要ではなく、結果からどのようなことが言えるのかの「仮説立て」をすることが大切です。
例えば、ある従業員のエンゲージメントが著しく低下していたとします。低下していることは単なる事実であるため、低下自体は問題ではありません。
エンゲージメントが著しく低下した背景や変化の原因を考えることが、エンゲージメントサーベイの結果を読み解くポイントになります。
エンゲージメント低下の「問題設定」を行う
ステップの2つ目は、「エンゲージメント低下の問題設定を行う」ことです。
エンゲージメントサーベイの結果を読み込んで、仮説立てをしたら、問題設定を行います。
例えば、特定部署で従業員のエンゲージメントが低下している場合、まずは何が問題なのかを洗い出します。
上司との関係性が悪化している
業務量の増加により負荷が高まっている
チーム内のコミュニケーションが不足している
上記のような要因が考えられるでしょう。
こうした仮説を立てたうえで、実際に事実を確認することが重要です。
対象部署にヒアリングするだけではなく、残業時間や勤怠情報など関連するデータも参照します。
その結果、上司との関係性悪化がエンゲージメント低下のトリガーだったとしたなら、上司と部下との関係改善を問題として設定し、課題解決に取り組むことがポイントです。
エンゲージメントに影響を及ぼす変数を見つける
ステップの3つ目は、「エンゲージメントに影響を及ぼす変数を見つける」ことです。
エンゲージメントは、以下のようなさまざまな変数によって左右されます。従業員のストレス
上司や同僚からの支援の有無
従業員の健康上の問題
これらの要因を整理・分析し、どの要素がエンゲージメントに最も強く影響しているかを見つけることが重要です。
変数の分析には、統計ツールを使用するのもよいですが、タレントマネジメントシステムを活用すれば簡単に分析できる場合もあります。
また、サーベイ項目と他のデータを掛け合わせ、相関関係を確認することもおすすめです。
例えば、「ワーク・エンゲージメント」の調査であれば、「活力・熱意・没頭」の3分類の質問項目に対して上司や先輩従業員との関係性に関わるデータをかけ合わせることで、仕事の面白さに上司との関係が影響する可能性がわかるかもしれません。
分析結果をもとに施策を検討する
ステップの4つ目は、「分析結果をもとに施策を検討する」ことです。
エンゲージメントサーベイで収集したデータの分析から、問題に対して影響を強く及ぼす変数が判明したら、その変数をどう変えるか施策を検討します。
例えば、従業員の健康状態が悪化しているなら、以下のような対策が考えられます。
健康指導を行う
従業員を休ませる
職場環境を変える
この時、問題に対して最も効果的な施策を検討することが重要です。
健康状態の改善であれば、単に休ませるだけでは、良い効果が出ない場合もあります。
従業員に健康指導を行ったうえで、しばらく休暇を与えるなど、根本的に解決ができる方法を検討するようにしましょう。
近年では、「従業員が職場での全ての時間で得られる価値経験」をあらわす、「エンプロイーエクスペリエンス(EX)」の考え方が浸透し始めています。
従業員が、高いエンゲージメントを維持して働ける会社づくりを行うには、単発的な職場環境の改善ではなく、従業員目線で「働く体験」の満足度を向上させる取り組みが必要です。
調査結果を従業員に必ずフィードバックする
ステップの5つ目は、「調査結果を従業員に必ずフィードバックする」ことです。
サーベイを実施した後は、結果と今後の改善方針を従業員に共有することが重要です。
課題によってはすぐに解決できないこともありますが、その場合でも「現状の把握内容」や「今後どのように取り組む予定か」を伝えましょう。
エンゲージメントサーベイで調査を実施した後に、何のアクションもないと、「アンケートに協力した意味はあったのか?」と従業員のモチベーションを下げてしまうおそれがあります。
それにより、今後調査を実施する際に、従業員の協力を得ることが難しくなってしまう場合があります。
従業員の声をもとに改善へ動いている姿勢を見せることで、信頼関係の構築やエンゲージメントの向上につながります。
調査を繰り返し行う
ステップの6つ目は、「エンゲージメントサーベイでの調査を繰り返し行う」ことです。
エンゲージメントサーベイで集めたデータをもとに、課題を見つけ出し、さまざまな施策を行っていく中で、時間が経つとまた新たに別の課題が発生する場合があります。
その場合、さらに改善施策を行う必要があるかもしれません。
また、従業員のエンゲージメントは常に変化するため、一度の調査だけで状況を把握し続けることはできません。
そのため、エンゲージメントサーベイは一度の調査結果だけではなく、半年〜1年の一定期間で、定期的に行う必要があります。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントサーベイツールの選び方
エンゲージメントサーベイツールを選ぶ際、どれを選べば良いのか分からないという悩みを持つ場合もあるでしょう。
エンゲージメントサーベイツールを選ぶ際の、3つのポイントについて確認してみましょう。
エンゲージメントサーベイツールの選び方
- ツールを使用する目的を明確にしてツールを選ぶ
- 高度な分析ができ操作性がよいツールを選ぶ
- レポート機能があるツールを選ぶ
ツールを使用する目的を明確にしてツールを選ぶ
エンゲージメントサーベイツールを選ぶ際のポイントの1つ目は、「ツールを使用する目的を明確にしてツールを選ぶ」ということです。
ツールの導入を検討している時点で、アンケートだけでは解決できない課題があるのではないでしょうか。
まずは、「集計作業の効率化を図りたい」「データ分析を客観的に行いたい」など、ツールを導入する具体的な目的を明確にしましょう。
そのうえで、簡単な調査であれば、Googleフォームなどの無料のアンケートツールと、質問項目の組み合わせで充分です。
一方で、詳細な分析やレポート作成を行いたい場合は、専用のエンゲージメントサーベイツールの導入が効果的です。
高度な分析ができ操作性がよいツールを選ぶ
2つ目は、「高度な分析ができ操作性がよいツールを選ぶ」ということです。
高度な機能を持つエンゲージメントサーベイツールを選んだものの、使いこなせないケースがあります。
もし、担当者がITやPC操作に不慣れであれば、直感的に操作できるツールを選ぶようにしましょう。
分析機能と操作性のバランスを見極め、自社の運用体制に合ったツールを選定することで効果を発揮することができます。
レポート機能があるツールを選ぶ
3つ目は、「レポート機能があるツールを選ぶ」ということです。
エンゲージメントサーベイツールを選ぶ際は、レポート機能が搭載されているツールを選ぶことを強くおすすめします。
一部のエンゲージメントサーベイツールでは、調査を実施したものの、結果の集計やレポートにまとめるのは手動という場合があります。
高度なレポート機能のあるツールであれば報告書の作成も印刷も不要になり、ツールの画面を共有するだけで報告が完了します。
業務工数を削減するためにも、レポート機能のあるツールを選ぶようにしましょう。
エンゲージメントサーベイのおすすめツール「HRBrain 組織診断サーベイ」

ここでは、エンゲージメントサーベイを成功に導くおすすめのツールとして「HRBrain 組織診断サーベイ」を紹介します。
エンゲージメントサーベイの導入から分析、施策実行までの過程で発生しがちな、「設問設計が難しい」「分析から具体的な改善アクションにつながらない」といった課題を網羅的に解決するサーベイツールです。
以下のような特徴があり、課題解決につながるエンゲージメントサーベイの実現を叶えられます。
設問を柔軟にカスタマイズできる
本格的な統計分析で組織改善につながる課題を特定できる
直感的な操作・判断で、誰でも簡単に利用できる
ツール利用から運用まで伴走サポートを提供している
サーベイを単なる現状把握で終わらせず、経営や現場を巻き込んだ具体的な組織改善アクションへとつなげるための強力なパートナーとなるでしょう。
エンゲージメントサーベイツールの活用事例
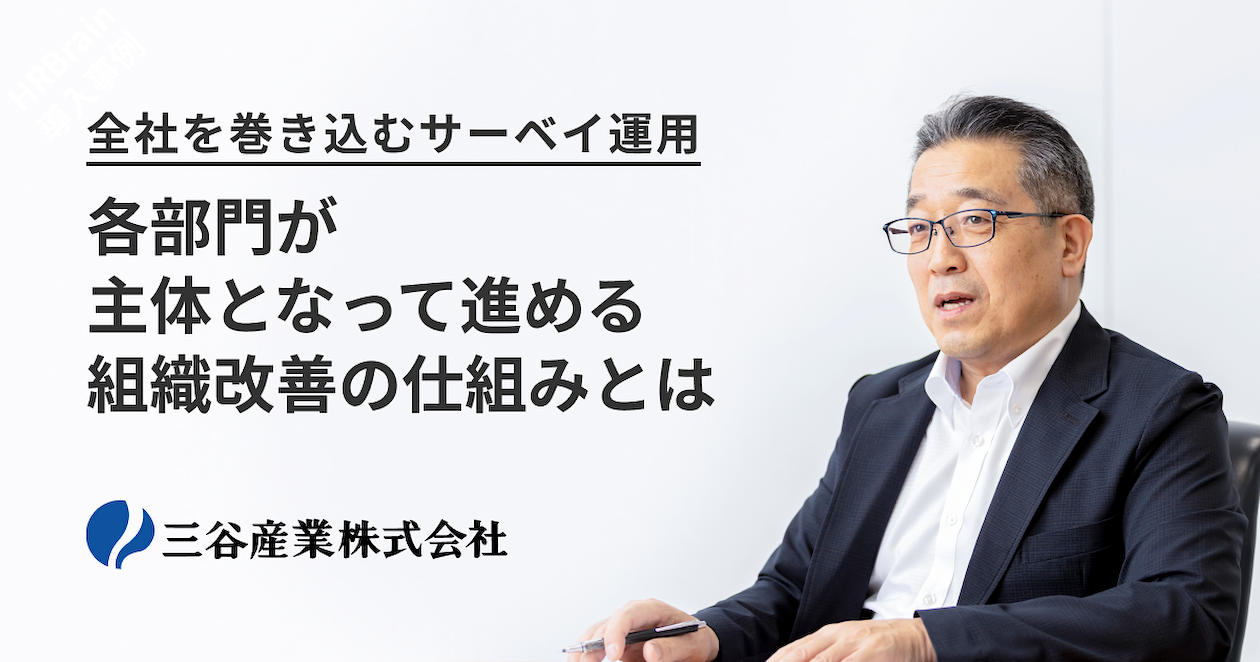
三谷産業株式会社では、従来のサーベイが実施間隔の長さや集計の遅さにより、リアルタイムで改善につなげられないという課題がありました。さらに、制度や運営の複雑さによって人事部門の負担が大きく、改善活動が継続できない状況にありました。
そのため「良い会社であり続けるための非財務的経営目標」の設定を進める中で、社員エンゲージメントを可視化する新たな仕組みが求められていました。
そこでHRBrainの「EX Intelligence」を導入し、組織の「実態」と「ありたい姿」のギャップを数値で把握できる体制を整えました。サーベイの分析は人事部門だけでなく各部門が主体的に実施し、6か月単位でPDCAサイクルを回す仕組みを導入しました。また、サーベイ結果を踏まえて1on1を実施し、上司が部下に対してポジティブアクションを行うなど、現場での対話や行動変革も進めました。
その結果、サーベイ結果をリアルタイムで把握できるようになり、迅速な改善活動が可能となりました。回答率はほぼ100%を達成し、エンゲージメントスコアも向上しました。さらに、人事部門の負担が軽減され、各部門が自律的に改善を進める仕組みが確立されたことで、全社を巻き込んだ持続的な組織改善が実現しています。
【関連コンテンツ】
エンゲージメントサーベイを活用し、組織課題を解決する一歩を踏み出しましょう
エンゲージメントサーベイは、従業員の自発的な貢献意欲を可視化し、組織課題を正しく把握するための強力なツールです。
従業員満足度調査やモラールサーベイと異なり、未来の行動につながる熱意を測る点が特徴であり、課題解決の精度を高めます。データを活用することで、施策の優先順位を明確にし、的確な人事戦略やチーム運営につなげられます。
また、離職防止や生産性向上、採用力強化など多くのメリットをもたらすのも大きな魅力です。まずはエンゲージメントサーベイを実施し、自社の課題を見える化する一歩を踏み出しましょう。







