タレントマネジメントとは?導入の目的や手順をわかりやすく解説
人材データの一元管理を実現し、あらゆる人事施策の実行をサポート
- タレントマネジメントとは
- タレントマネジメントが注目される背景
- 労働人口減少による人材不足
- 働き方の多様化
- グローバル人材の育成
- 人的資本経営の実現
- タレントマネジメントの目的
- 経営目標の達成
- 戦略的な人材開発
- 柔軟な部署連携
- タレントマネジメントで得られる効果
- 中長期的な人材開発・後継者育成
- 適材適所の人員配置
- 公正な人事評価
- 従業員のエンゲージメント向上
- タレントマネジメントの導入手順
- STEP1:目的を設定する
- STEP2:自社のマネジメントの現状を知る
- STEP3:採用・育成計画を作成する
- STEP4:人材計画を実施する
- STEP5:分析と運用の見直し
- タレントマネジメントの活用事例
- 日産自動車株式会社
- GE(ゼネラル・エレクトリック)
- タレントマネジメントを成功させる3つのポイント
- 従業員の理解を得る
- 管理職の教育を行う
- タレントマネジメントシステムを導入する
- タレントマネジメントシステムとは?
- タレントマネジメントシステムの主な機能
- タレントマネジメントシステムの注意点
- タレントマネジメントシステムの導入事例
- 人事関連業務を効率化|JA三井リース株式会社
- 人事評価と人材情報を一元管理|NGB株式会社
- 人事評価制度を刷新|株式会社日比谷花壇
- タレントマネジメントシステムを活用して効率的な人事戦略を成功させよう
企業の成長において、人材は重要な経営資源です。しかし、どれだけ優秀な人材を採用しても、その能力を正しく把握し、適切に配置・育成できなければ、本来のパフォーマンスを発揮できません。
そこで注目されているのが、タレントマネジメントという考え方です。従業員一人ひとりのスキルやキャリア志向を可視化し、経営戦略に沿った配置や育成を行うことで、組織全体の競争力を高められます。
本記事では、タレントマネジメントの目的や具体的な導入手順、成功企業の事例まで、実践に必要な情報を解説します。
タレントマネジメントとは
タレントマネジメントとは、社員の能力・スキルや経験、適性などを体系的に管理し、経営戦略の実現に向けて最適な配置・育成・評価を行う人材マネジメント手法です。
「タレント(才能)」という言葉が示すとおり、社員一人ひとりが持つ強みや可能性を最大限に引き出すことを目指します。
従来の人事管理では、採用・配置・評価といった業務が個別に行われ、データも部門ごとに分散していました。一方、タレントマネジメントでは、スキル情報や評価履歴だけでなく、キャリア志向や資格、配置履歴なども統合的に管理し、経営戦略と連動させる点が特徴です。
この仕組みにより、後継者の育成計画づくりや適材適所の配置、社員のモチベーション向上など、多岐にわたる人事施策の推進を可能にします。
タレントマネジメントが注目される背景
タレントマネジメントが多くの企業で導入されている背景には、現代のビジネス環境における4つの変化が挙げられます。
労働人口減少による人材不足
働き方の多様化
グローバル人材の育成
人的資本経営の実現
それぞれの背景を理解したうえで、自社にタレントマネジメントが必要かどうかを判断しましょう。
労働人口減少による人材不足
少子高齢化を背景に日本の労働人口は減少し、多くの業界で人材の獲得競争が激化しています。中途採用市場でも、優秀な人材の確保は容易ではありません。
こうした状況下では、新たに採用するよりも既存の人材を育成・活用することが現実的な選択肢となります。
そこで、タレントマネジメントを導入すれば、社内に眠っている人材の可能性を発掘できます。たとえば、営業部門で実績を上げている社員が、データ分析のスキルも持ち合わせていた場合、その能力を活かして新規事業の企画担当に抜擢することも可能です。
限られた人材を最大限に活用する仕組みとして、タレントマネジメントの重要性が高まっています。
働き方の多様化
近年、リモートワークやフレックスタイム、副業解禁など、働き方の選択肢は急速に広がりました。社員の価値観も変化し、ワークライフバランスやキャリア自律を重視する傾向が強まっています。そのため、画一的な人事制度では、こうした多様なニーズに対応できません。
タレントマネジメントでは、個々の社員のキャリア志向や働き方の希望を把握し、柔軟な配置や育成計画を設計できます。
たとえば、育児中の社員には在宅勤務を前提としたプロジェクトを割り当て、スキルアップを目指す若手にはジョブローテーションの機会を提供するといった対応が可能です。
社員一人ひとりの状況に合わせたマネジメントを実現することで、離職率の低下や組織への定着率向上にもつながります。
グローバル人材の育成
企業活動のグローバル化が進むなか、海外市場で活躍できる人材の育成は必要不可欠です。語学力だけでなく、異文化理解や現地マネジメントのスキルを持つ人材が求められていますが、こうした能力は短期間で身に付くものではありません。
タレントマネジメントを活用すれば、将来的にグローバル展開を担う人材を早期に特定し、計画的な育成が可能です。具体的には、語学研修や海外拠点への短期派遣、異文化コミュニケーション研修などを組み合わせた育成プログラムの設計が挙げられます。
また、すでに海外経験を持つ社員を可視化することで、急な海外プロジェクトにも迅速に対応できる体制を構築できます。
人的資本経営の実現
人的資本経営とは、「人材を資本と捉え、投資によって企業価値を高める」考え方です。近年、企業価値を測る指標として人的資本への注目が高まっています。
2023年には、上場企業を対象に人的資本情報の開示が義務化され、投資家やステークホルダーに対して人材戦略の説明が求められるようになりました。具体的には、人材への投資額や育成計画、ダイバーシティの推進状況などを数値化し、経営戦略との関連性を提示する必要があります。
タレントマネジメントは、人的資本経営を実現するための基盤です。社員のスキルデータや育成状況、配置計画などを可視化することで、人材投資の効果を測定し、外部に説明できる体制が整います。
タレントマネジメントの目的
タレントマネジメントを導入する目的は企業によって異なりますが、多くの場合、以下の3つに集約されます。
経営目標の達成
戦略的な人材開発
柔軟な部署連携
自社がどの目的を重視するかを明確にすることで、タレントマネジメントの導入がスムーズに進みます。
経営目標の達成
タレントマネジメントの最大の目的は、経営目標を達成させるための経営戦略を人事面からバックアップし実現させることです。
そのためには、まず企業の主力となる優秀なリーダー人材を育成することが、最重要項目です。短期的には、タレントマネジメントによって、業務効率の改善につなげることもできますが、そこは本質的な面ではありません。あくまで、経営目標の達成にどのように活かせるのかを考えることが重要です。
戦略的な人材開発
社員のスキルアップは、企業の競争力を左右する要素です。しかし、場当たり的なスキルアップ研修では十分な効果は得られません。
タレントマネジメントでは、個々の社員の現在のスキルレベルやキャリア志向、業務経験を踏まえたうえで、個別育成計画を作成できます。
たとえば、営業職として5年のキャリアを持つ社員が、将来的にマネジメント職を目指している場合には、リーダーシップ研修や予算管理の実務経験、部下指導のOJTなどの段階的な提供が可能です。
同時に、後継者育成計画と連動させることで、将来的に重要ポジションを担える人材情報データを形成できます。
戦略的な人材開発によって組織全体のスキルレベルが底上げされ、外部環境の変化にも柔軟に対応できる組織へと成長します。
柔軟な部署連携
柔軟な部署連携は、経営目標の達成に比べればやや短期的ですが、人事領域ではよくありがちな課題の一つです。
特に企業規模が大きくなるほど、人材配置における問題に直面します。規模が大きくなり縦割り体制になると、それぞれの部署との連携が上手くいかなくなり、結果的に業務効率の悪化を招きます。
タレントマネジメントでは、全社員のスキル・経験・適性を一元管理するため、部門を横断した人材活用が可能です。
スキルが可視化されれば、「〇〇の業務なら●●さんに任せよう」と部署ではなく、従業員個人へ業務を引き継げるようになり、よりフレキシブルなコミュニケーション促進にもつながります。
タレントマネジメントで得られる効果
タレントマネジメントを導入すると、単なる人事管理の効率化にとどまらず、組織全体の競争力を高めるような以下の効果が期待できます。
中長期的な人材開発・後継者育成
適材適所の人員配置
公正な人事評価
従業員のエンゲージメント向上
上記の4つの効果を理解したうえで、自社への導入を検討しましょう。
【関連コンテンツ】
中長期的な人材開発・後継者育成
タレントマネジメントを活用すると、将来の経営を担う人材を計画的に育成できます。多くの企業が直面する課題は、重要なポジションに就く人材が突然退職した際、後任者が見つからないという事態です。
タレントマネジメントでは、後継者育成計画を通じて、重要ポジションごとに候補者を複数名リストアップし、段階的に育成できます。
たとえば、営業部長の後継者を育成する場合、現時点で営業実績が優れている課長クラスの社員を特定し、3年間の育成計画を立てます。その後は、予算管理の実務経験や他部門との連携プロジェクトのリーダー、経営会議への参加といった段階を経て、マネジメントスキルの習得が可能です。
さらに、個別育成計画を活用することで、社員一人ひとりのキャリア目標に合わせた育成プログラムも提供できます。結果として、社員の成長実感が高まり、離職率の低下も期待できるでしょう。
適材適所の人員配置
タレントマネジメントでは、全社員のスキルや経験、キャリア志向などを一元管理できるため、最適な人材配置を実現できます。
タレントマネジメントを導入すると、「どの社員がどのスキルをどの程度持っているか」を可視化できるようになります。
そのため、必要なときに必要な社員を部門横断で即座に特定可能です。また、9ボックスという評価手法を用いることで、社員のパフォーマンスと成長可能性を9つの区分に分類し、適切な配置戦略を立てられます。
その結果、従業員は自分の強みを活かして働けることで仕事への満足度も高まり、効率的な事業運営につながるでしょう。
公正な人事評価
タレントマネジメントでは、客観的なデータに基づいた人事評価が可能です。タレントマネジメントシステムを活用すると、評価基準をスキルやコンピテンシー(行動特性)、業績といった具体的な項目に分解し、数値化できます。
たとえば、業職であれば「売上達成率」「新規顧客獲得数」といった定量指標と、「問題解決能力」「リーダーシップ」といった定性指標を組み合わせて評価します。
また、評価データを蓄積することで、評価者による偏りを発見・是正でき、全社で評価基準を統一する取り組みが可能です。公正な評価制度は社員の納得感を高め、モチベーション向上や組織への信頼構築につながります。
従業員のエンゲージメント向上
タレントマネジメントは、社員のエンゲージメント(組織への愛着心や貢献意欲)を高める効果があります。
社員が組織に定着し、高いパフォーマンスを発揮するには、自分のキャリア目標が会社で実現できるという実感が必要です。
タレントマネジメントでは、個別育成計画を通じて、社員一人ひとりのキャリア志向を把握したうえで育成機会を提供できます。会社が自分のキャリアを真剣に考えてくれているという実感が湧くことで、組織への愛着形成にもつながります。
また、スキルの可視化により、社員自身が自分の強みや成長を客観的に把握することも可能です。定期的なフィードバック面談を通じて、現状のスキルレベルや成長度合い、今後の目標を明確にすることで、成長実感が得られ、仕事へのモチベーション向上にも期待できます。
タレントマネジメントの導入手順
タレントマネジメントを効果的に導入するには、計画的なステップを踏む必要があります。以下の5つのステップに沿って進めることで、自社に適したタレントマネジメントを構築できます。
STEP1:目的を設定する
STEP2:自社のマネジメントの現状を知る
STEP3:採用・育成計画を作成する
STEP4:人材計画を実施する
STEP5:分析と運用の見直し
STEP1:目的を設定する
タレントマネジメント導入の最初のステップは、何のために導入するのかという目的を明確にすることです。目的があいまいなまま進めると、現場の協力が得られず、形だけの取り組みに終わってしまいます。
目的設定では、経営戦略と連動させることがポイントです。たとえば「3年後に海外売上を30%にする」という経営目標があれば、「グローバル人材の育成と配置最適化」がタレントマネジメントの目的になります。
目的を設定する際は、経営層や人事部門を巻き込み、全社で共通認識を持つことが重要です。目的が明確になれば、次のステップで何を調査し、どのデータを整備すべきかが見えてきます。
STEP2:自社のマネジメントの現状を知る
目的を設定したら、次は自社の現状を把握します。人材管理に関連する従業員の人数・スキル・目標・評価など、情報を数字やデータとして可視化しましょう。そのなかで人事戦略と比較し「できている」「できていない」のギャップを把握します。
タレントマネジメントは中長期的に実施されるため、関連部署との協力が必要不可欠です。たとえば、従業員のデータ共有やヒアリングのお願いなどがスムーズにできるよう、根回しをしておきます。従業員データは常に最新情報をアップデートできる体制を整えるのがポイントです。
STEP3:採用・育成計画を作成する
現状把握ができたら、経営目標を達成するために必要な採用・育成計画を作成します。その際には、「いつまでに、どのようなスキルを持つ人材を、何名確保するか」という具体的な設計が必要です。
採用計画では、社内育成では間に合わないスキルや、希少性の高い専門スキルを持つ人材を外部から採用する方針を決めます。一方、育成計画では既存社員のスキルアップや、後継者候補の育成プログラムを設計しましょう。
計画作成時には、必要な人材を確保するまでの期間を考慮し、余裕を持ったスケジュールを組むことが成功のポイントです。
STEP4:人材計画を実施する
計画が完成したら、実際に採用・育成・配置を実行します。このステップでは、計画を現場に落とし込み、継続的に運用できる仕組みを構築することがポイントです。
実施段階では、現場のマネージャーや従業員に対して、タレントマネジメントの目的や運用方法を丁寧に説明し、協力を得ることが必要不可欠です。
特に「なぜこの評価手法を使うのか」「なぜスキル情報を登録する必要があるのか」を理解してもらわないと、データの精度が低下し、効果が出ません。定期的な説明会や研修を実施し、全社でタレントマネジメントを運用する体制を整えましょう。
STEP5:分析と運用の見直し
計画の実施期間が終了したら、継続的な効果測定・改善作業が必要です。
このステップでは、KGIやKPIをダッシュボードで可視化し、定期的にモニタリングします。設定すべきKPIの例としては「重要ポジションの充足率」「離職率」「育成完了率」などです。
これらの指標を毎月または四半期ごとに確認し、目標に対する進捗状況を把握します。また、現場からのフィードバックを収集し、運用上の課題の洗い出しも重要です。
「スキル情報の入力が手間」「評価基準がわかりにくい」といった声があれば、システムの改善や評価基準の再設計を検討しましょう。
マネジメントの基本や手順・ポイントについて、詳しく知りたい方は「【完全版】人材マネジメントの基本・事例・役立つシステムまで」をご確認ください。
タレントマネジメントの活用事例
タレントマネジメントに取り組んだ企業事例を2社紹介します。
日産自動車株式会社
GE(ゼネラル・エレクトリック)
【関連コンテンツ】
日産自動車株式会社
日本の大手自動車メーカーの日産自動車株式会社。タレントマネジメントを始め人材育成の先進的な企業です。優秀な人材を発掘・育成する「キャリアコーチ」と呼ばれる社内スカウトマンが存在し、世界中にいる優秀人材を見極める役割があります。また優秀人材に求める人物像や条件・ポジションを明確にすることで、各ポジションに合う人材候補を把握し育成するスタイルを採っています。
GE(ゼネラル・エレクトリック)
世界最大のアメリカ合衆国の総合電機メーカーのGE(ゼネラル・エレクトリック)。元祖タレントマネジメントの実践企業として有名です。現在はタレントマネジメントを実施していませんが、かつては「9ブロック」と呼ばれる9つの表を作成し人材をあてはめて、リーダー候補となる人材を評価するタレントマネジメント手法を採っていました。
▼「タレントマネジメント」についてもっと詳しく
タレントマネジメントを成功させる3つのポイント
タレントマネジメントを成功に導くためには、組織全体で取り組む体制を整えることが重要です。以下の3つのポイントを押さえることで、タレントマネジメントを効果的に機能させられます。
従業員の理解を得る
管理職の教育を行う
タレントマネジメントシステムを導入する
それぞれのポイントについて、具体的に解説します。
従業員の理解を得る
タレントマネジメントを成功させるには、現場で働く従業員の協力が欠かせません。目的や意義を理解していないと「余計な業務が増えた」と感じ、スキル情報の登録や評価への協力が得られなくなるためです。
導入初期に説明会を開催し、「なぜタレントマネジメントを始めるのか」「どのようなメリットがあるのか」を丁寧に伝えましょう。特に、キャリアアップの機会が増えることや最適な人員配置が実現すること、成長を会社が支援してくれることなど、従業員にとっての具体的なメリットを示すことが効果的です。
従業員が、自分のためになる仕組みだと実感できれば、積極的に参加してもらいやすくなるでしょう。
管理職の教育を行う
管理職は、タレントマネジメントの運用において中心的な役割を担います。部下のスキル評価や育成計画の作成、フィードバック面談の実施など、多くの場面で管理職の適切な判断や行動が必要です。
しかし、新しい評価手法やシステムの操作が管理職にとって負担に感じられることもあります。そのため、導入前に管理職向けの研修を実施し、評価方法やシステムの活用方法、効果的なフィードバックの伝え方などを習得してもらいましょう。
また、「なぜこの評価が必要なのか」という背景まで理解してもらうことで、形式的な運用ではなく、本質的な人材育成につながります。管理職が適切にタレントマネジメントを運用できれば、組織全体でのスムーズな定着が期待できます。
タレントマネジメントシステムを導入する
タレントマネジメントを効率的に運用するには、専用のシステム導入が効果的です。Excelでの管理では、データの更新や検索に手間がかかり、部門横断での情報共有も困難です。
タレントマネジメントシステムを活用すると、全従業員のスキルや評価、配置履歴などを一元管理でき、条件検索で必要な人材を即座に特定できます。
また、後継者計画や育成進捗をダッシュボードで可視化し、リアルタイムでモニタリングできるため、迅速な意思決定が可能になります。
人事評価に特化したものや採用管理が強いものなど、システムによって特徴が異なるため、システム選定の際は自社の目的に合った機能を持つかを確認しましょう。
【関連コンテンツ】
タレントマネジメントシステムとは?
タレントマネジメントシステムとは、従業員の能力やスキル・経験、評価などの人材情報を一元管理し、配置・育成・評価を効率的に行うためのITツールです。従来、各部門がExcelや紙で個別に管理していたデータを統合することで、全社で活用できる形にします。
このシステムを導入することで、人事担当者は膨大なデータを手作業で集計する手間から解放され、戦略的な人材活用に時間を使えるようになります。
タレントマネジメントシステムにはさまざまな種類があり、機能や価格帯も幅広く存在するため、自社の課題や目的に合ったシステムを選ぶことが重要です。
タレントマネジメントシステムの主な機能
タレントマネジメントシステムには、人材管理を効率化する多様な機能が搭載されています。
育成計画の管理
タレントマネジメントを推進する際は、経営目標に基づいて人材育成計画を実施します。立てた計画が順調に進捗しているか、またどの人材にどのスキルをセットすれば良いのか、計画立案や進捗のサポートをしてくれるため、人材育成計画が円滑に進みます。
従業員のスキル・能力を一元管理
システムで従業員のスキルや能力の一元管理が可能です。今まで見えていなかったスキルの可視化はもちろん、実績や適性、異動履歴なども把握できるため、人材マネジメントがより効率化します。
後継管理
データにより一元管理することで、リーダーシップを持つ人材の欠員や役割の重複、また適任の人材をいち早く発掘できます。特に、手薄になりがちな海外事業部の業務引き継ぎ、リーダーシップを持つ人材のヘッドハンティングなどがスムーズに行えます。
目標管理
従業員に見合った目標を立て、その目標に向けてそれぞれ能力開発、人材マネジメントを行います。事業部ごとにバラバラにまとめられているものを、一括でシステムでデータ管理することで、個人単位あるいは組織単位での目標管理が円滑に進みます。
タレントマネジメントシステムの注意点
タレントマネジメントはあくまで手段であり、使い方を間違えれば、期待以上の効果を得られないだけでなく、逆効果になることもあります。
管理する人材が増えて対応が追いつかない
M&Aなどにより事業拡大や子会社設立・海外支社の立ち上げなど、事業を拡大しようとすれば、必要な人材の数はどんどん増えていきます。特に、グローバル展開を行う企業の場合、その土地に合わせた採用も必要です。採用する人材の幅が広がった結果、一部の従業員しか管理できていないという状態に陥り、形骸化してしまうリスクがあります。
部署間の連携が難しい
タレントマネジメントでは、従業員個人を管理するため、部署間のいわゆるスキマにあたる業務や役割が発生した際には、部署同士で密に連携して、タレントマネジメントの推進を行う必要があります。そのためには、部署間の壁を突破できるリーダーシップを持つ人材が求められます。
タレントマネジメントシステムの導入事例
実際にタレントマネジメントシステムを導入し、成果を上げている企業の事例を紹介します。
人事関連業務を効率化|JA三井リース株式会社
人事評価と人材情報を一元管理|NGB株式会社
人事評価制度を刷新|株式会社日比谷花壇
各社がどのような課題を抱え、どのように解決したのかを知ることで、自社への導入イメージが具体的になります。
人事関連業務を効率化|JA三井リース株式会社
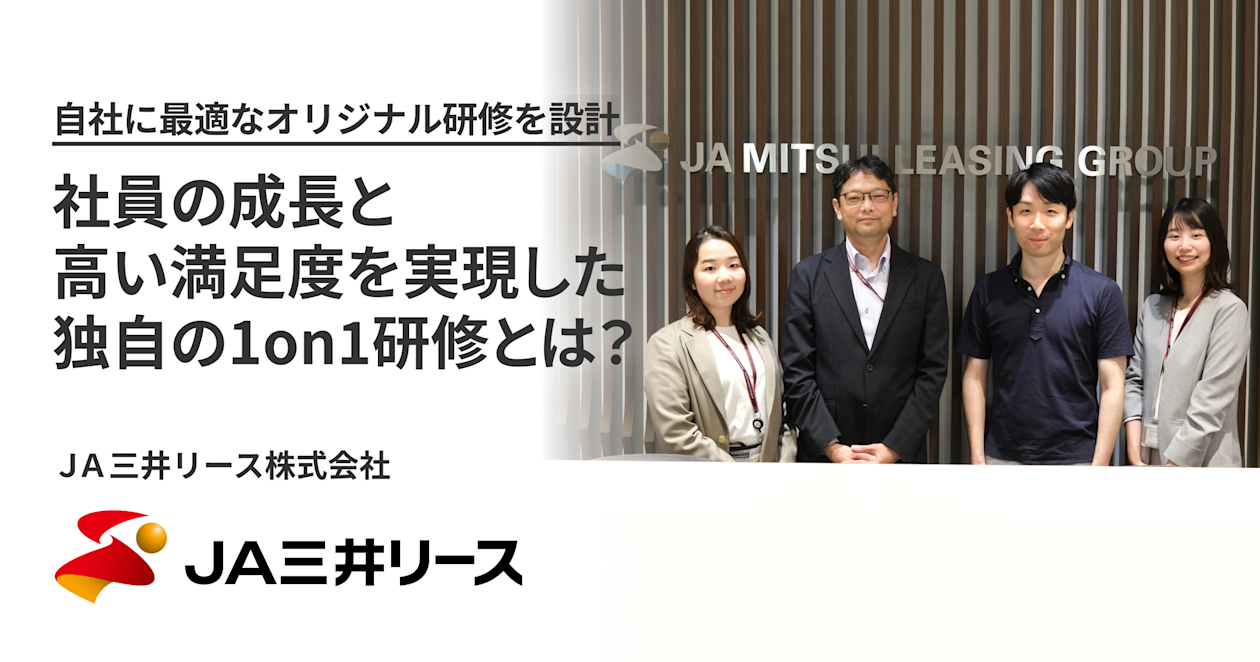
JA三井リース株式会社では、人事情報がExcelやPDFなどさまざまな形式で点在しており、評価業務で手動集計が発生していました。恒久的な業務改善を目指して、直感的に使えるユーザーインターフェースと、人事評価業務の効率化という目的への合致により、HRBrainの導入を決めました。
導入後は従業員情報が一元化され、必要な情報をすぐに取り出せるようになりました。また、異動直後の役職者が自分で部下の情報を確認できるようになり、業務効率が大幅に向上しました。
【関連コンテンツ】
人事評価と人材情報を一元管理|NGB株式会社
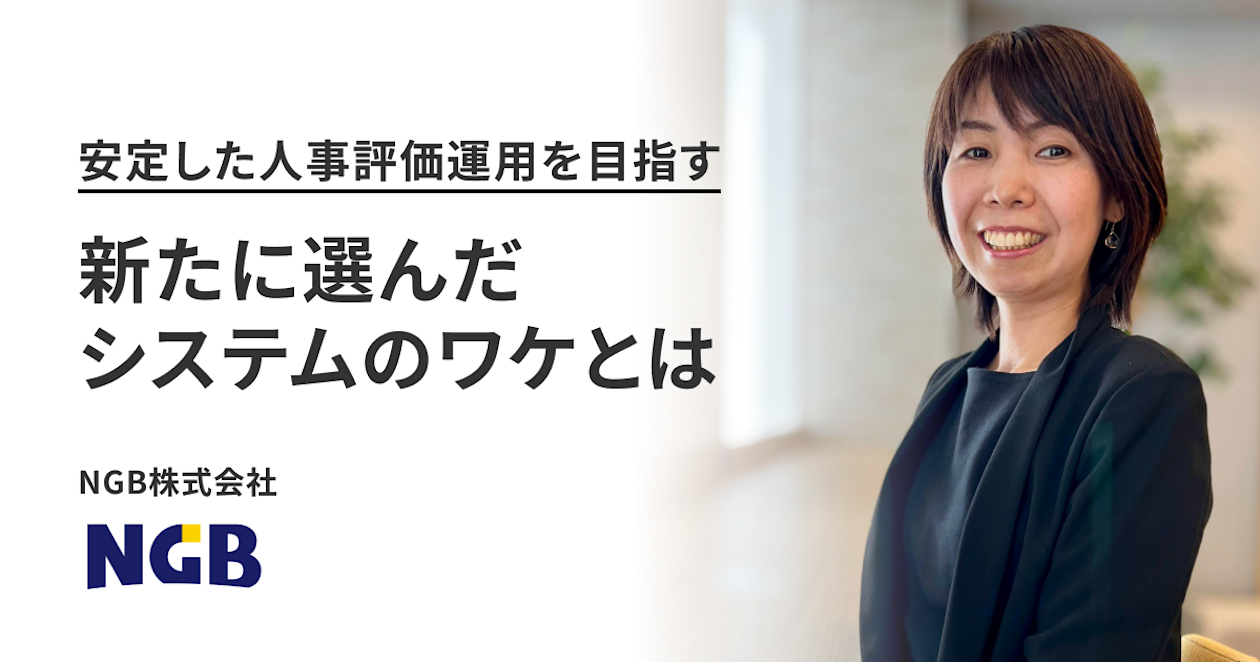
NGB株式会社では、人事評価システムのエラー頻発や進捗管理の困難さ、またタレントマネジメントシステムの設定の複雑さという課題を抱えていました。これら2つのシステムを運用する手間も負担となっており、安定した人事評価運営を目指してHRBrainを導入しています。
導入後は評価プロセスの可視化により進捗管理が容易になり、システム一本化でコスト削減と業務効率化を実現しました。社員名簿には趣味情報も登録し、上司と部下の面談時のアイスブレイクに活用されています。
また、配置シミュレーション機能を活用することで、簡単な操作で組織全体のバランスを見ながら検討できるため、適材適所の人材配置検討にも役立てられています。
【関連コンテンツ】
人事評価制度を刷新|株式会社日比谷花壇

株式会社日比谷花壇では、20年間見直されていなかった人事評価制度の基準があいまいで、上長によって評価にバラつきがあるという課題を抱えていました。また、各店舗にパソコンが1台しかないため、目標入力も難しいという状況でした。
そこで、簡単な操作性に惹かれHRBrainを導入しました。導入後はスマホから目標入力できるようになり、設立以来初めて対象従業員全員が目標を入力できました。
社員名簿には得意分野や今後やりたいことなどを登録したり、自ら必要な資格を確認して取得したりする動きも生まれ、キャリアに活かすという動きも出ています。全国に拠点がある同社では、顔写真とパーソナル情報を確認できるようになり、役職者から評価しやすくなったという声も上がっています。
【関連コンテンツ】
タレントマネジメントシステムを活用して効率的な人事戦略を成功させよう
タレントマネジメントは、企業の持続的な成長を支える重要な経営戦略です。従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、経営目標の達成につなげる仕組みを構築することで、組織全体の競争力が高まります。
導入にあたっては、明確な目的設定や現状把握、継続的な改善などのステップを段階的に踏むことが重要です。また、従業員の理解を得ることや管理職の教育を行うこと、適切なシステムを導入することの3つのポイントを押さえることで、効果的な運用が実現します。
タレントマネジメントシステムの導入により、人事業務の効率化に加えて、公正な評価や適材適所の配置、計画的な育成が可能です。自社の課題に合わせたタレントマネジメントの仕組みを設計することで、効率的に人事戦略を実現させましょう。







