ワークエンゲージメントの測定方法は?質問項目や成功事例を解説
組織状態の把握から分析・課題抽出までワンストップで実現
- ワークエンゲージメントの主な3つの測定方法
- UWES(ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度)
- MBI-GS(マスラック・バーンアウト・インベントリー)
- OLBI(オルデンバーグ・バーンアウト・インベントリー)
- ワークエンゲージメントを測定する際の5つの注意点
- 目的が曖昧なまま導入しない
- 心理的安全性を守るための配慮を徹底する
- 測定バイアスを避ける設計と運用の工夫を行う
- アンケートの形骸化を防ぐ仕組みを整える
- 経営層・マネジメント層の関与を確保する
- ワークエンゲージメントを高める方法
- おすすめのエンゲージメント向上ツール「HRBrain」
- エンゲージメント向上の成功事例2選
- 人事業務効率化とエンゲージメント向上を推進|C-United株式会社
- 「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みを推進|株式会社鴻池組
- ワークエンゲージメントを正しく測定し改善に役立てよう
従業員の活力や熱意、仕事への集中状態を表すワークエンゲージメントは、組織の生産性や成長に直結する重要な指標です。
だからこそ、自社のワークエンゲージメントを的確に把握し、課題に応じた対策を講じていくことが求められます。
本記事では、ワークエンゲージメントの主な測定方法として広く活用されている「UWES」「MBI-GS」「OLBI」と、それぞれの質問項目のポイント、具体的な活用方法について徹底解説しました。
成功事例も交えて紹介していくので、自社に最適な方法を整理し、従業員の活力に満ちた職場づくりに役立てて下さい。
また、ワークエンゲージメントについてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連コンテンツもぜひご覧ください。
【関連コンテンツ】
ワークエンゲージメントの主な3つの測定方法
ここでは、組織の持続的成長を支える重要な指標であるワークエンゲージメントの測定方法について紹介します。 ワークエンゲージメントの測定には主に以下の3つの方法があります。
<ワークエンゲージメントの主な測定方法>
測定方法 | 詳細 |
|---|---|
UWES(ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度) | 力・熱意・没頭の3要素から構成される測定法 |
MBI-GS(マスラック・バーンアウト・インベントリー) | バーンアウトの逆指標としてエンゲージメントを評価 |
OLBI(オルデンバーグ・バーンアウト・インベントリー) | 疲弊と離脱の2要素で測定するシンプルな手法 |
【関連コンテンツ】
UWES(ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度)
UWES(Utrecht Work Engagement Scale)は、オランダ・ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らによって開発された、ワークエンゲージメントを直接測定する最も信頼性の高い尺度です。
UWESでは、ワークエンゲージメントを以下3つの要素から評価します。
要素 | 詳細 |
|---|---|
活力(Vigor) | 仕事へのエネルギーや粘り強さ |
熱意(Dedication) | 仕事への誇りややりがい |
没頭(Absorption) | 仕事への集中や夢中になる状態 |
UWESの特徴は、ポジティブな心理状態を直接測定できる点にあり、日本語版も島津明人教授らによって標準化され、厚生労働省の調査でも採用されています。自律性ややりがいを重視する職場文化を持つ企業に特に適しており、従業員のモチベーションやパフォーマンス向上のための具体的な施策立案に役立ちます。
ただし、ポジティブな項目が中心のため、職場の問題点の発見には不向きな面もあります。導入時には商用利用のライセンス確認が必要ですが、学術的裏付けのある信頼性の高い測定が可能です。
UWESの測定方法
UWESの測定方法は、各質問項目に対して下記の7段階で回答を求め、各因子および全体の平均値を算出する方式です。
段階 | 点数 |
|---|---|
全く感じない | 0 |
ほとんど感じない | 1 |
めったに感じない | 2 |
時々感じる | 3 |
よく感じる | 4 |
とてもよく感じる | 5 |
いつも感じる | 6 |
これにより従業員の心理状態をより詳細に数値化できます。UWESには17項目版、9項目版、3項目版があり、組織規模や目的に応じて柔軟に選択できます。
特に9項目版は、活力・熱意・没頭の各要素をそれぞれ3項目で測定し、回答者の負担と精度のバランスがとれているため実務でよく使用されます。
測定結果は単に全体スコアだけでなく、3つの因子別のスコアも分析することで、例えば「熱意は高いが活力が低い」といった具体的な課題が見えてきます。
また、部門別、役職別、年齢層別などの属性分析と組み合わせることで、組織のどの層にどのような課題があるかを特定し、より効果的な施策立案が可能です。日本人労働者の平均スコアと比較することで、自社の立ち位置を客観的に把握することもできます。
UWESの質問項目
UWESの質問項目は「活力」「熱意」「没頭」の3つの要素について、従業員の主観的な体験に焦点を当て、「どの程度の頻度でその状態を感じるか」を測定します。
UWESの質問項目をそのまま使用することも可能ですが、自社の文化や職種に合わせて表現を微調整することで、従業員の理解度を高め、より正確な測定ができます。ただし、質問の本質を変えないよう、専門家の助言を得ながら行うことが望ましいでしょう。
具体例を下記に記載いたしますので、参考にしてください。
<17項目版>
No. | 項目 | カテゴリ |
|---|---|---|
1 | 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる | 活力 |
2 | 自分の仕事に、意義や価値を大いに感じる | 熱意 |
3 | 仕事をしていると、時間がたつのが速い | 没頭 |
4 | 職場では、元気が出て精力的になるように感じる | 活力 |
5 | 仕事に熱心である | 熱意 |
6 | 仕事をしていると、他のことはすべて忘れてしまう | 没頭 |
7 | 仕事は、私に活力を与えてくれる | 熱意 |
8 | 朝に目がさめると、さあ仕事へ行こう、という気持ちになる | 活力 |
9 | 仕事に没頭しているとき、幸せだと感じる | 没頭 |
10 | 自分の仕事に誇りを感じる | 熱意 |
11 | 私は仕事にのめり込んでいる | 没頭 |
12 | 長時間休まずに、働き続けることができる | 活力 |
13 | 私にとって仕事は、意欲をかきたてるものである | 熱意 |
14 | 仕事をしていると、つい夢中になってしまう | 没頭 |
15 | 職場では、気持ちがはつらつとしている | 活力 |
16 | 仕事から頭を切り離すのが難しい | 没頭 |
17 | ことがうまく運んでいないときでも、幸福感をもって仕事をする | 活力 |
(参考:ワーク・エンゲイジメント(UWES)|慶應義塾大学総合政策学部島津研究室)
<9項目版>
No. | 項目 | カテゴリ |
|---|---|---|
1 | 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる | 活力 |
2 | 職場では、元気が出て精力的になるように感じる | 活力 |
3 | 仕事に熱心である | 熱意 |
4 | 仕事は、私に活力を与えてくれる | 熱意 |
5 | 朝に目がさめると、さあ仕事へ行こう、という気持ちになる | 活力 |
6 | 仕事に没頭しているとき、幸せだと感じる | 没頭 |
7 | 自分の仕事に誇りを感じる | 熱意 |
8 | 私は仕事にのめり込んでいる | 没頭 |
9 | 仕事をしていると、つい夢中になってしまう | 没頭 |
(参考:ワーク・エンゲイジメント(UWES)|慶應義塾大学総合政策学部島津研究室)
<3項目版>
No. | 項目 | カテゴリ |
|---|---|---|
1 | 仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる | 活力 |
2 | 仕事に熱心である | 熱意 |
3 | 私は仕事にのめり込んでいる | 没頭 |
(参考:ワーク・エンゲイジメント(UWES)|慶應義塾大学総合政策学部島津研究室)
MBI-GS(マスラック・バーンアウト・インベントリー)
MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)は、ワークエンゲージメントの対極にあるバーンアウト(燃え尽き症候群)を測定することで、間接的にエンゲージメントの状態を評価する尺度です。
バーンアウトとワークエンゲージメントは負の相関関係にあるため、バーンアウトのリスクが高い従業員や部門を特定することで、予防的なエンゲージメント向上施策を講じることができます。
MBI-GSは、以下3つの要素から構成されており、職場でのストレス要因を多角的に把握できます。
疲労感(Exhaustion)
冷笑的態度(Cynicism)
職務効力感(Professional Efficacy)
特に業務過多やストレス管理を重視する現場、離職率の高さやメンタルヘルス不調者の増加に悩む企業に適しています。
MBI-GSの強みは問題の早期発見にあり、特に離職リスクの高い従業員の発見や、職場環境の改善に役立ちます。
【関連コンテンツ】
MBI-GSの測定方法
MBI-GSの測定方法は、各質問項目に対して「まったくない」から「毎日」までの頻度を尋ねる形式で、「疲労感」「冷笑的態度」「職務効力感」の3つの下位尺度のスコアを算出します。
段階 | 点数 |
|---|---|
全く感じない | 0 |
ほとんど感じない | 1 |
めったに感じない | 2 |
時々感じる | 3 |
よく感じる | 4 |
とてもよく感じる | 5 |
いつも感じる | 6 |
一般的にMBI-GSは合計16項目の質問で構成され、各下位尺度は5~6項目で測定されます。「疲労感」と「冷笑的態度」のスコアが高く、「職務効力感」のスコアが低いほど、バーンアウトの傾向が強いと解釈され、逆の場合はエンゲージメントが高いと間接的に判断できます。
測定結果を分析する際は、単にハイリスク者の検出だけでなく、各下位尺度のスコアパターンから組織的な課題を読み取ることが重要です。
例えば、特定の部門で「職務効力感」が低い場合、達成感の不足や承認の欠如が課題である可能性が高く、それに応じた施策を検討すべきでしょう。
また、属性別(部門、役職、年齢層など)の分析も組み合わせることで、より具体的な改善策の立案が可能になります。
MBI-GSの質問項目
MBI-GSの質問項目は、バーンアウトの3つの側面に関する具体的な状態や感情を問うもので、職場でのネガティブな心理反応を包括的に把握できます。
以下に質問項目の例を記載します。
No. | 項目(一例) | カテゴリ |
|---|---|---|
1 | 1日の仕事が終わると疲れ果ててぐったりすることがある | 疲労感 |
2 | 仕事のために心からへとへとに疲れていると感じる | 疲労感 |
3 | 自分がしている仕事の意味や大切さがわからなくなることがある | 冷笑的態度 |
4 | 自分の仕事に対する熱意が少なくなったと思う | 冷笑的態度 |
5 | 自分は職場で役に立っていると思うことがある | 職務効力感 |
6 | 職場で起こる問題を効果的に解決できる | 職務効力感 |
MBI-GSの質問はネガティブな内容を含むため、実施時には目的を丁寧に説明し、匿名性を確保するなどの配慮が必要です。
また、結果のフィードバックでは問題点の指摘だけでなく、改善に向けた具体的なサポート方針も合わせて伝えることで、建設的な組織変革につなげることができます。
OLBI(オルデンバーグ・バーンアウト・インベントリー)
OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)はドイツの研究者らによって開発されたバーンアウト測定尺度です。
MBI-GSよりもシンプルな2因子構造を持ち、エンゲージメントの逆指標を評価します。
要素 | 詳細 |
|---|---|
疲弊(Exhaustion) | 仕事による慢性的な身体的・情緒的・認知的疲労感 |
離脱(Disengagement) | 仕事への関心喪失や心理的距離 |
OLBIの特徴は、バーンアウトをより簡潔な枠組みで捉えることで、組織内の問題点を明確に特定しやすい点にあります。
また、肯定的な表現と否定的な表現がバランス良く含まれており、回答バイアスを低減する効果も期待できます。
OLBIはワークロードや働き方改革に取り組む企業に適しており、ある地方金融機関では業務負荷が高い部門を特定し、繁閑調整を実施することでプレゼンティーズム(出勤はしているが生産性が低下している状態)の防止に成功しています。
特に「離脱」の指標は離職リスクの早期発見に有効で、MBI-GSよりも設問数が少なく構造がシンプルであるため、定期的なモニタリングやパルスサーベイとして活用しやすい利点があります。
OLBIの測定方法
OLBIの測定方法は、各質問項目に対して、以下4段階で回答を求め、スコアを算出します。
段階 | 点数 |
|---|---|
全くそう思わない | 1 |
ほとんどそう思わない | 2 |
たまにそう思う | 3 |
とてもそう思う | 4 |
一般的にOLBIは合計16項目の質問で構成され、「疲弊」と「離脱」の各要素が8項目ずつで測定されます。
肯定的な項目は逆転処理された上でスコア化され、両要素のスコアが高いほどバーンアウトの傾向が強く、エンゲージメントが低い状態と解釈されます。
測定結果を分析する際は、2因子のバランスに注目することが重要です。例えば「疲弊」スコアが高く「離脱」が低い場合は、従業員が疲労しながらも仕事への関与を維持している状態で、長期的にはバーンアウトリスクが高まる可能性があります。
このようなパターンを早期に発見し、適切な休息や業務調整などの対策を講じることが効果的です。定期的に測定し、スコアの変化を追跡することで、組織の状態変化を早期に把握し、タイムリーな介入が可能になります。
OLBIの質問項目
OLBIの質問項目は「疲弊」と「離脱」の2因子に関する具体的な状態や感情を問うもので、各因子について肯定的表現と否定的表現の両方を含むバランスの取れた構成となっています。
No. | 項目(一例) | カテゴリ |
|---|---|---|
1 | 仕事の前にすでに疲労感がある | 疲弊 |
2 | 仕事のために精神的に消耗していると感じる | 疲弊 |
3 | 仕事に集中して打ち込めない | 離脱 |
4 | 最近、仕事への熱意を失いつつある | 離脱 |
5 | 仕事をしていると活力を感じる(逆転項目) | 疲弊 |
6 | 仕事に対して熱意を持っている(逆転項目) | 離脱 |
「離脱」については「仕事に集中して打ち込めない」「最近、仕事への熱意を失いつつある」などがあります。また肯定的表現としては「仕事をしていると活力を感じる」「仕事に対して熱意を持っている」(逆転項目)などが含まれます。
このバランスのとれた質問構成により、回答バイアスを低減し、より正確なデータ収集が可能になります。
OLBIの質問項目は、従業員の身体的・精神的な疲労状態と仕事への心理的距離感を多面的に捉えることができ、特に働き方改革や業務効率化に取り組む組織では、施策の効果を検証する指標としても活用できます。
測定結果は、職場環境改善や業務プロセス見直し、1on1ミーティングの充実などの具体的な取り組みにつなげていくことが重要です。
ワークエンゲージメントを測定する際の5つの注意点
ここでは、ワークエンゲージメント測定を効果的に実施するために欠かせない注意点について紹介します。
ワークエンゲージメント測定を成功させるには主に以下の点に注意する必要があります。
<ワークエンゲージメントを測定する際の5つの注意点>
目的が曖昧なまま導入しない
心理的安全性を守るための配慮を徹底する
測定バイアスを避ける設計と運用の工夫を行う
アンケートの形骸化を防ぐ仕組みを整える
経営層・マネジメント層の関与を確保する
目的が曖昧なまま導入しない
ワークエンゲージメント測定を導入する際に最も重要なのは、「なぜ測定するのか」という目的を明確にすることです。
「話題だから」「他社が導入しているから」といった理由だけでは、測定後の具体的な活用が難しくなります。目的が曖昧なままでは、適切な測定ツールの選定ができず、収集したデータを有効活用できません。
また、従業員にとっても「なぜこのサーベイに回答する必要があるのか」が理解できず、回答の質や率が低下してしまいます。
目的としては、「離職率の低下」「生産性の向上」「メンタルヘルス不調の予防」「組織風土の改善」「人的資本の情報開示対応」など具体的なものが考えられます。例えば離職率の改善が目的なら、バーンアウト傾向も測定できるMBI-GSやOLBIが適している可能性が高く、働きがいの向上を重視するならUWESのようなポジティブな心理状態を直接測定するツールが適しています。
目的設定では、「新入社員の3年後定着率を現在の70%から85%に向上させる」など、できるだけ具体的で測定可能な目標を設定し、経営層からマネージャー、一般従業員まですべての階層に丁寧に説明することが重要です。
【関連コンテンツ】
心理的安全性を守るための配慮を徹底する
ワークエンゲージメント測定で信頼性の高いデータを得るためには、従業員が本音で回答できる環境を整える必要があります。
「回答内容が上司に知られるのではないか」「ネガティブな回答をすれば評価に影響するのではないか」といった不安があると、従業員は本当の状態や感情を表明できません。そのため、匿名性の担保や回答内容の取り扱いに関する倫理的配慮を徹底することが不可欠です。
具体的には、「完全な匿名性の保証」「個人が特定されない形でのデータ処理」「回答の任意性の明示」「人事評価とは完全に切り離すことの保証」などが挙げられます。
特にMBI-GSやOLBIのようなネガティブな内容を含む尺度を使用する場合は、測定の目的や結果の活用方法を丁寧に説明することが重要です。心理的安全性の確保は技術的な対応だけでなく、日頃からの信頼関係構築が基盤となります。
サーベイ実施前のコミュニケーションを丁寧に行い、疑問に真摯に応えることで、より率直で有益な回答を得ることができます。
また、結果のフィードバックも透明性をもって行い、実際に回答をもとにした改善活動を目に見える形で実施することで、次回以降の測定における信頼性も向上します。
【関連コンテンツ】
測定バイアスを避ける設計と運用の工夫を行う
ワークエンゲージメント測定では、回答者のバイアスやデータの偏りを最小限に抑えるための工夫が重要です。
人間の回答には様々なバイアスが生じがちです。例えば「良く見られたいという意識から理想的な回答をしてしまう」「極端な選択肢を選びがち」「中間的な回答を選びがち」といったバイアスを考慮せずにデータを解釈すると、誤った結論や施策につながるおそれがあります。
バイアスを低減するための工夫としては、OLBIのように肯定的・否定的表現のバランスを取った質問項目の設計、適切な回答選択肢の数の検討、実施時期の工夫、回答者属性の偏りをチェックする仕組みなどが挙げられます。
また、複数の情報源を組み合わせて多角的に状況を把握することも有効です。
測定バイアスを完全に排除することは難しいですが、その存在を認識し、適切に対処することで、より信頼性の高いデータ収集と分析が可能になります。特に経年変化を追跡する場合は、毎回同じ条件で実施し、変化の解釈をより正確にすることが大切です。
アンケートの形骸化を防ぐ仕組みを整える
ワークエンゲージメント測定を継続して実施する中で、多くの企業が直面するのが「アンケート疲れ」や「サーベイの形骸化」という問題です。
サーベイを実施しても結果が適切にフィードバックされなかったり、具体的な改善行動につながらなかったりすると、次第に従業員の関心や期待が薄れ、形式的な回答に陥りがちになります。
これでは質の高いデータが得られず、せっかくの測定が無駄になってしまいます。形骸化を防ぐための効果的な施策は、以下の通りです。
測定結果の迅速なフィードバック
具体的な改善アクションの明示とその進捗報告
前回からの変化の可視化
参加型の改善活動の実施
成功事例の共有と称賛
ワークエンゲージメント測定は「測って終わり」ではなく、継続的な改善サイクルの一部であることを認識し、従業員が「自分たちの声が実際に組織改善につながっている」と実感できる仕組みを整えることが、形骸化を防ぎ、エンゲージメント向上の文化を醸成する鍵となります。
【関連コンテンツ】
経営層・マネジメント層の関与を確保する
ワークエンゲージメント測定と改善活動を成功させるためには、経営層とマネジメント層の積極的な関与と強いコミットメントが不可欠です。
エンゲージメント向上は人事部門だけで実現できるものではなく、組織全体の取り組みとして位置づける必要があります。経営層の関与がなければ必要なリソース(時間、予算、人員)が確保できず、マネジメント層の関与がなければ現場レベルでの具体的な改善が進みません。
また、従業員にとっても、経営層がこの取り組みを重視していることが伝われば、回答の真剣さや改善活動への参加意欲が高まります。
経営層・マネジメント層の関与を促す方法は、以下の通りです。
経営会議での定期的な報告と議論
経営層からのメッセージ発信
部門長の業績評価にエンゲージメントスコアを組み込む
マネジャー向けの研修やコーチング
経営層に対しては、エンゲージメント向上が離職率低下、生産性向上、顧客満足度向上といった経営指標に直結するというデータや、ESG投資や人的資本開示などの外部要請を示すことで、戦略的重要性を訴求することが効果的です。
マネジメント層には、1on1ミーティングの実施方法や部下のエンゲージメントを高める具体的なスキルを提供し、日常のマネジメント活動の中でエンゲージメント向上に取り組める環境を整えましょう。
【関連コンテンツ】
ワークエンゲージメントを高める方法
ワークエンゲージメントを高めるには、「JD-Rモデル(Job Demands-Resourcesモデル)」に基づいたアプローチが有効とされています。
このモデルでは、エンゲージメントを高める鍵として「仕事の資源」と「個人の資源」の充実が重要だと示されています。
仕事の資源には、適切な業務量の調整、フィードバックや評価の納得感、キャリア開発の機会などが含まれます。例えば、上司が1on1ミーティングを通じて部下の負荷を把握し、業務量を適正に保つことで、過度なストレスや燃え尽き(バーンアウト)を防ぎながら、やりがいや達成感を促進できます。
また、従業員の業務に対する姿勢や意欲を高めるには、評価やフィードバックの質も重要です。自分の仕事が正当に評価され、フィードバックを通じて成長の方向性が見えると、モチベーションは大きく向上します。
一方、個人の資源とは、自己効力感(自分はできるという感覚)や楽観性、レジリエンス(困難を乗り越える力)といった、心理的に前向きな状態を指します。
これらを育むには、従業員にとって挑戦的だが達成可能な業務を任せたり、仕事とプライベートにメリハリを持たせたりすることが重要です。
適度な難易度の業務を通じて成功体験を重ねることは、自己肯定感の向上にもつながります。また、十分な休息をとり、心理的にも仕事から離れる時間を確保することで、ストレスをリセットし、次の業務への活力を取り戻すことができます。
このように、仕事と個人の両面から資源を充実させる取り組みは、ワークエンゲージメントを高め、従業員の定着や生産性向上にも寄与します。組織としては、制度や仕組みだけでなく、日々のマネジメントや職場環境のあり方を見直し、働きがいのある職場づくりを意識することが求められます。
【関連コンテンツ】
おすすめのエンゲージメント向上ツール「HRBrain」

HRBrainは、従業員のエンゲージメントを可視化し、組織改善に繋げるためのクラウドサービスです。
部門別や属性別に分析できるダッシュボードや、課題ごとに対策を講じやすいレポート出力も強みです。導入により、エンゲージメント低下の兆候を早期に察知し、組織改善のアクションにつなげやすくなります。
従業員のモチベーションや定着率向上を目指す企業にとって、HRBrainは効果的な一手となるでしょう。
組織の課題解決と従業員の働きがい向上を同時に実現するHRBrainのサービスについて、詳しい資料や導入事例にご興味のある方は、ぜひ下記リンクよりお問い合わせください。
エンゲージメント向上の成功事例2選
ここでは、実際の企業がワークエンゲージメント向上に成功した具体的な事例について紹介します。 エンゲージメント向上の成功事例として、以下2社の取り組みをチェックしていきましょう。
<エンゲージメント向上の成功事例2選>
人事業務効率化とエンゲージメント向上を推進|C-United株式会社
「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みを推進|株式会社鴻池組
人事業務効率化とエンゲージメント向上を推進|C-United株式会社
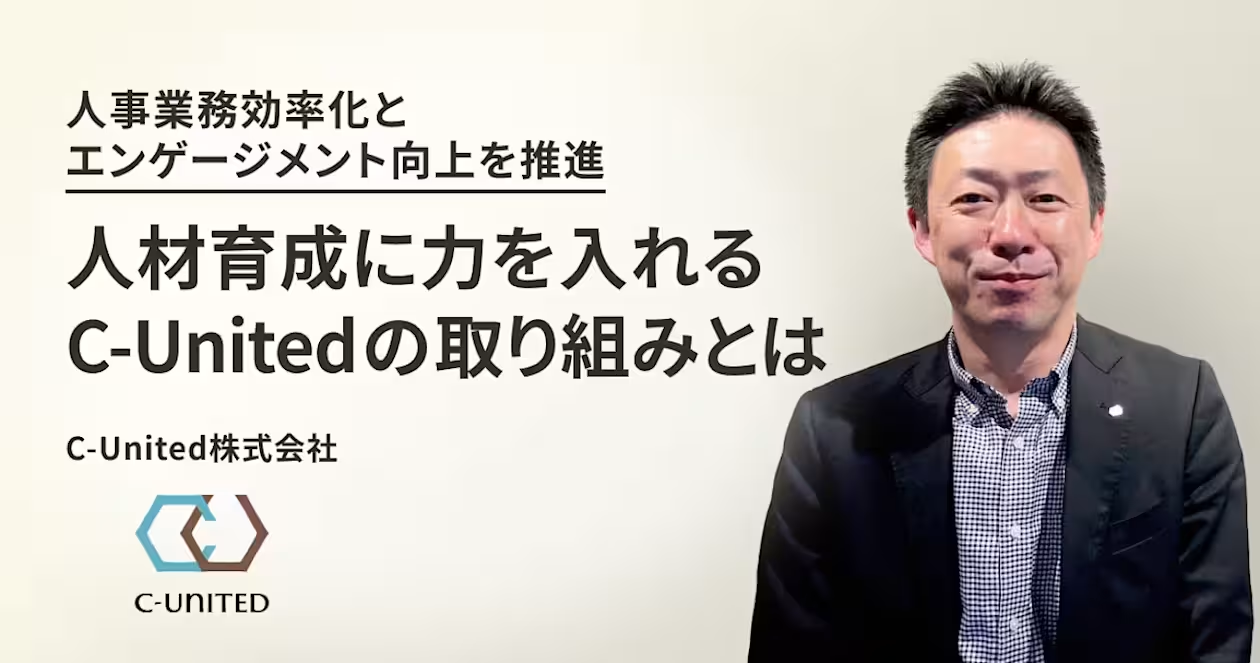
C-United株式会社では、従来、紙ベースでの人事評価運用により年間約1,700時間もの業務工数が発生していました。加えて、会社統合やコロナ禍といった環境変化により、従業員の不安感が高まり、離職にもつながるなど、人的資源の維持に課題を抱えていました。
このような背景を踏まえ、同社は2021年11月よりHRBrainを導入し、人事評価業務のシステム化を推進しました。従業員の声を可視化し、組織課題を明確にするため、2022年8月からは組織診断サーベイ「EX Intelligence」も併せて活用しています。導入の決め手は、導入後の手厚いサポート体制と、システムの柔軟なカスタマイズ性でした。
これらの取り組みにより、人事評価にかかる膨大な作業時間が大幅に削減され、評価の公平性や納得感を高めるプロセスへと時間を充てられるようになりました。また、サーベイによって従業員の声をスコアで可視化できるようになり、具体的な課題に応じた改善策を講じることが可能となりました。同社は今後もHRBrainとEX Intelligenceを連携活用し、エンゲージメントの向上と経営理念の実現を目指していく方針です。
【関連コンテンツ】
「従業員エンゲージメント業界No.1」実現に向けた取り組みを推進|株式会社鴻池組

株式会社鴻池組は、創業150年の節目にあたり、持続的成長を見据えた長期ビジョン「KONOIKE ONE VISION 2050」を策定し、「従業員エンゲージメント業界No.1」を掲げる挑戦を開始しました。
その背景には、入社後のミスマッチによる早期離職や、企業理念の社内浸透の低さといった組織課題がありました。特に、理念やメッセージを発信しているつもりでも、社員に十分伝わっていないという実感があり、組織と社員の認識ギャップを解消する必要があったのです。
こうした課題に対し、同社は従来の満足度調査から脱却し、エンゲージメントに着目した組織診断サーベイ「EX Intelligence」を導入しました。満足度ではなく、社員の「期待値」と「実感値」のギャップに着目することで、どの施策に優先的に取り組むべきかが明確になり、経営層とも具体的な議論がしやすくなった点が評価されています。
さらに、ダッシュボードでの即時分析やHRBrainの分析サポートにより、結果をスピーディーに現場にフィードバックし、若手研修などの具体的施策に展開できるようになりました。
現在は、EX Intelligenceのスコアを中期経営計画のKPIとして設定し、エンゲージメントを「見える化」することで、施策の成果を継続的に追跡可能な状態にしています。
【関連コンテンツ】
ワークエンゲージメントを正しく測定し改善に役立てよう
ワークエンゲージメントは、従業員の活力・熱意・没頭といった前向きな働き方を可視化する重要な指標です。
代表的な測定方法には、ポジティブ要素を直接測る「UWES」、バーンアウト傾向から逆算する「MBI-GS」、シンプルで定期測定に適した「OLBI」があり、目的に応じて使い分けることが効果的です。
まずは自社に合った指標を選定し、継続的に測定・分析を行うことで、組織課題の早期発見や施策の改善に役立ちます。エンゲージメント向上の第一歩として、適切な測定ツールを導入し、従業員の声に耳を傾けましょう。







